ドストエフスキーの日本への影響
ドストエフスキーは我が国に長い間、影響を与えてきている。ここでは日本への影響、関わり方を自分なりにまとめたい。
項目としては、
- ドストエフスキーの受容史、理解史
- 作家等のドストエフスキーへの関心
- 作家に与えた影響
と整理上分類できる。
「作家等のドストエフスキーへの関心」と「作家に与えた影響」
の二つは区別が分かりにくいかもしれない。「ドストエフスキーへの関心」とは我が国の著名な作家等がドストエフスキーをどう評価していたか、の問題である。「作家に与えた影響」とはドストエフスキーに感銘、あるいは心酔し、自らの創作に影響を受けた、という意味である。後者は前者の部分集合である。
日本での受容史
内田魯庵による『罪と罰』の翻訳は、明治25〜26年に刊行されている。小説の前半部分のみで英訳から重訳である。ドストエフスキーの没年は明治14年であるから、その約十年後には翻訳が出されているわけである。
明治時代には一部の作家に影響を与えた(後述)。ただし一般読者はドストエフスキーの小説としては『罪と罰』以外には、『虐げられた人々』などしか翻訳で読めなかった。
大正時代は白樺派によって人道主義作家として知られた。また不完全な形とは言え、多くの小説も翻訳されるようになった。
昭和になり、シェストフなどが紹介され、『地下室の手記』以降の諸作品を中心にしたドストエフスキー理解が始まる。これは現在まで続く流れであろう。
(続く)
著名作家はドストエフスキーをどう評価していたのか。
夏目漱石(慶応3年〜大正5年、1867〜1916)
漱石の著作でドストエフスキーの言及があるのは『思い出すことなど』(明治44年)である。その第20節と21節でドストエフスキーを語っている。しかしながら小説を論じているわけでない。
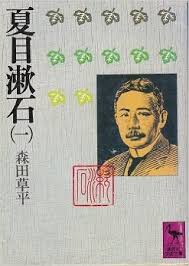

漱石はこの前年、いわゆる修善寺の大患を経験し、危うく死にかけた。病気と死からの生還について、自分とドストエフスキーの体験を比較している。
ドストエフスキーは癲癇が始まる際、恍惚的とも言える瞬間があったと書いている。漱石は大患の吐血後、精神状態はかなり普通とかけ離れたものとなったそうだ。(第20節)
第21節では、死刑宣告を受けた後のドストエフスキー、大患によって「少しの間死んでいた」漱石、これらの死からの生還を論じている。
漱石のドストエフスキーの作家論の類は自分の知っている限り、弟子森田草平(明治24年〜昭和24年、1881〜1949)の書いた、『夏目漱石』にある。昭和17年刊のこの著は講談社学術文庫で読める。
「漱石とドストエフスキー」と題された章の大部分は、森田自身のドストエフスキー観や漱石との比較であるが、漱石の言として次がある。
「その昔漱石先生は、私があまりにしばしばドストエフスキーを口にするのを見て、
「なにもドストエフスキーが描くような異常な局面ばかりが深刻な人生を示唆するものとはかぎらない。もっと平凡な人生のうちに深刻な人生を暗示するものがいくばくもある」といって私をいましめられた。私はそれに対して返す言葉はない。しかしながら、先生は異常な経験をもたれず、またそれに興味も持たれなかったために、日常の些末な事件のうちに人生の深刻味を発揮された。(中略)それに対して、ドストエフスキーは人生の可能性をあくまで押しつめていったために、ああいったような作品が生まれた。両方ながらそれでいではないか。」
(森田草平『夏目漱石(一)』、講談社学術文庫、昭和55年、p.78)
森田草平は作家であり、漱石の弟子の一人である。しかしながらドストエフスキー好きにとっては『悪霊』の本邦初訳(英訳から)者として記憶されている。『悪霊』という訳名も彼以来による。
『思い出すことなど』に戻る。この作品でドストエフスキーを論じる第20節は次のように書きだされる。
「ツルゲニェフ以上の芸術家として、有力なる方面の尊敬を新たにしつつあるドストイェフスキーには、人の知るごとく、小供の時分から癲癇の発作があった。」
これを読むと漱石の理解によれば(当時の文壇の理解でもあろう)、ドストエフスキーが明治の終わりころからツルゲーネフ以上に評価され出してきた、ということになる。
実際ツルゲーネフは明治時代に今では想像できないくらい評価され、読まれていたのである。二葉亭四迷の翻訳によるツルゲーネフの『あひゞき』(明治21年)は、言文一致体に大きな影響を与えたとされている。また小説家としてよく読まれていたのである。明治25年に『罪と罰』の翻訳が出ているものの、売れ行き不振で前半だけしか刊行されなかったドストエフスキーとはえらい違いである。
田山花袋の小説『蒲団』(明治40年)で主人公の作家が、女弟子に買わせた本を覚えているか。ツルゲーネフ全集である。明治時代からツルゲーネフ全集があったのか、と思って小説を確認したら英訳本である。丸善で買ったことになっている。
現在の評価と昔のそれとは異なる。当たり前すぎるように思えるが、時々現在の見方や評価が不変と勘違いしてしまう例は珍しくない。
大正時代の白樺派によるドストエフスキー理解に至る一つの経過報告のようなものである。
『明暗』のドストエフスキー
創作では絶筆となった『明暗』(大正5年)の第35~36回でドストエフスキーが出てくる。
以下はその箇所である。
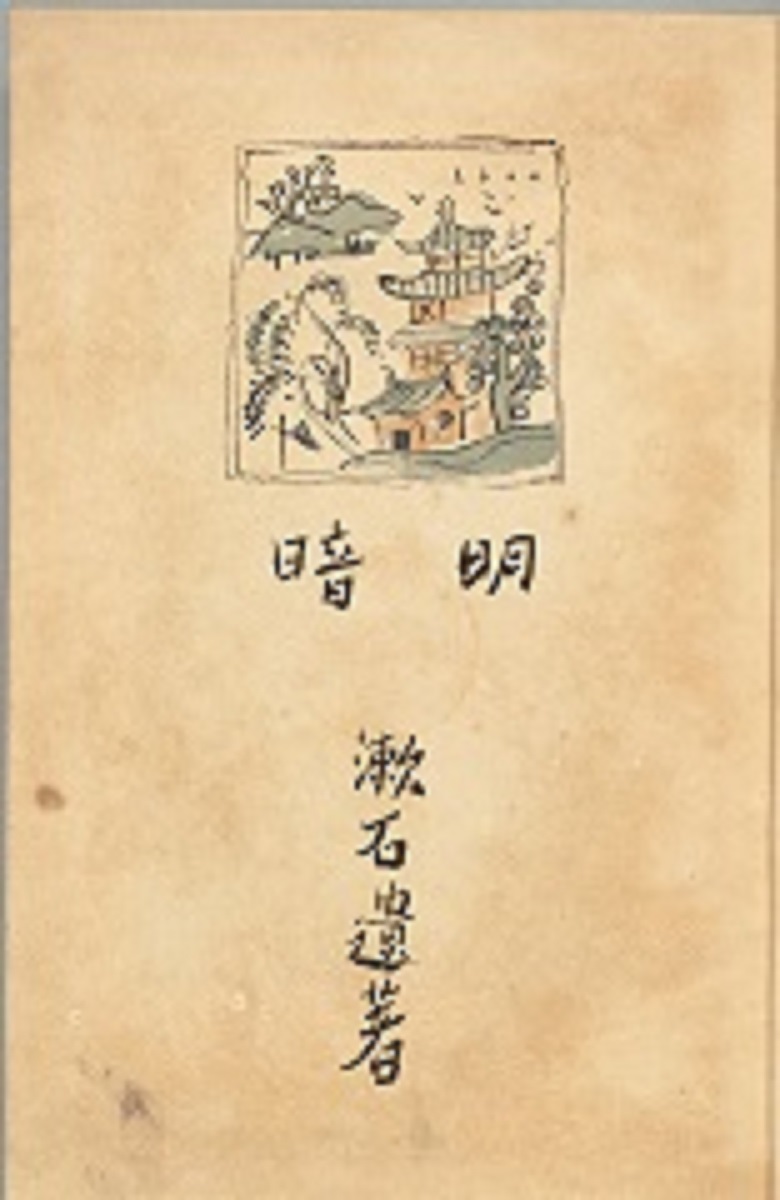
「彼ら(引用者注、土方や人足)は君や探偵よりいくら人間らしい崇高な生地(きじ)をうぶのままもってるか解らないぜ。ただその人間らしい美しさが、貧苦という塵埃(ほこり)で汚(よご)れているだけなんだ。つまり湯に入れないから穢(きた)ないんだ。馬鹿にするな」
小林の語気は、貧民の弁護というよりもむしろ自家(じか)の弁護らしく聞こえた。しかしむやみに取り合ってこっちの体面を傷(きずつ)けられては困るという用心が頭に働くので、津田はわざと議論を避けていた。すると小林がなお追(おっ)かけて来た。
「君は黙ってるが僕のいう事を信じないね。たしかに信じない顔つきをしている。そんなら僕が説明してやろう。君は露西亜(ロシア)の小説を読んだろう」
露西亜の小説を一冊も読んだ事のない津田はやはり何とも云わなかった。
「露西亜の小説、ことにドストエヴスキの小説を読んだものは必ず知ってるはずだ。いかに人間が下賤(げせん)であろうとも、またいかに無教育であろうとも、時としてその人の口から、涙がこぼれるほどありがたい、そうして少しも取り繕(つくろ)わない、至純至精の感情が、泉のように流れ出して来る事を誰でも知ってるはずだ。君はあれを虚偽と思うか」
「僕はドストエヴスキを読んだ事がないから知らないよ」
「先生に訊(き)くと、先生はありゃ嘘(うそ)だと云うんだ。あんな高尚な情操をわざと下劣な器(うつわ)に盛って、感傷的に読者を刺戟(しげき)する策略に過ぎない、つまりドストエヴスキがあたったために、多くの模倣者が続出して、むやみに安っぽくしてしまった一種の芸術的技巧に過ぎないというんだ。しかし僕はそうは思わない。先生からそんな事を聞くと腹が立つ。先生にドストエヴスキは解らない。いくら年齢(とし)を取ったって、先生は書物の上で年齢を取っただけだ。いくら若かろうが僕は……」
小林の言葉はだんだん逼(せま)って来た。しまいに彼は感慨に堪(た)えんという顔をして、涙をぽたぽた卓布(テーブルクロース)の上に落した。
三十六
不幸にして津田の心臓には、相手に釣り込まれるほどの酔が廻っていなかった。同化の埒外(らちがい)からこの興奮状態を眺める彼の眼はついに批判的であった。彼は小林を泣かせるものが酒であるか、叔父であるかを疑った。ドストエヴスキであるか、日本の下層社会であるかを疑った。そのどっちにしたところで、自分とあまり交渉のない事もよく心得ていた。彼はつまらなかった。また不安であった。感激家によって彼の前にふり落された涙の痕(あと)を、ただ迷惑そうに眺めた。
(以下略)
(青空文庫より)
『明暗』の主人公、津田(30歳の会社員)が友人の小林と酒場で語り合う場面である。ドストエフスキーを論じる小林の言に出てくる「先生」とは、津田の叔父、藤井だろう。
この先生はドストエフスキーに対して批判的な意見を吐き、これは弟子の森田草平に語った漱石に似ている。またこの小林という男は全く不快な人物として描かれている。ところでこの先生の理解はナボコフの意見と似ていないか。
日記及び断片のドストエフスキー
『白痴』関係
大正4年11月12日(金)に『白痴』の引用がある。
“Idiot”ノ中ニPrince Myshkinガgeneralノ妻君ト娘ニ話ヲスル中ニDostoievsky自身ノ経歴ノ如キ者ヲ挿話トシテ述ベタ條ニ曰ク:−
(昭和41年発行の岩波漱石全集第13巻、p.792)
としてムイシュキンが話す死刑執行に直面した心情の英訳が長々と引用されている。
同年11月17日(水)では癲癇の症状が、これも『白痴』の英訳で引用されている。
癲癇病の心状(The Idiotノ中ヨリ)
(以下英訳の文が続く)
(昭和41年発行の岩波漱石全集第13巻、p.797)
『白痴』第2篇第5節にある、癲癇発作の直前の異常な、恍惚ともいえる状態の描写のところである。
明治四十三・四年の断片にも『白痴』関係の2行がある。
〇Dostoiewskieノepileptic
死刑ヲ受ケタルアトノ心。
この2行は下を中括弧 } で括ってある。
(昭和41年発行の岩波漱石全集第13巻、p.592)
ニーチェとドストエフスキー
大正四年・五年頃の断片(日付不明)にニーチェから始まり、ドストエフスキーに言及する英文がある。これも引用であろうと思われるが、自分の持っている昭和41年発行の岩波漱石全集第13巻には注も何もなく不明である。(同書、p.785)
晩年のニーチェはドイツ至上主義やあらゆるナショナリズムを嫌っていた、などがあって最後は「真実な物は何もなく、凡てが許される」という考えは普通の人と同じく少数(の優れた者)にとっても危険である、で終わっている。
大正四年・五年頃の断片(日付不明)に次のような一行がある。説明も何もなし。
〇DostoievskiトMaeterlinck
(昭和41年発行の岩波漱石全集第13巻、p.786)
大正5年の日記及断片(日付不明)に次のような文がある。
〇Life 露西亜の小説を読んで自分と同じ事が書いてあるのに驚ろく。そうして只クリチカルの瞬間にうまく逃れたと逃れないとの相違である。という筋
(昭和41年発行の岩波漱石全集第13巻、p.835)
この「露西亜の小説」には注がついていて「漱石がこの時分に読んでいたドストエフスキーの小説であろう」とある。(同書、p.915)どの小説のどのあたりか気になる。
他人が聞いた漱石の言として、上で論じた森田の著のほか、次が残されている。
「近頃、僕のところへ来る若い人達はMerejkowskiの、TolstoiとDostoievskyに大変感服して批評の典型のように云っているが、僕はうまく書いてはあると思うが感心はせんね。先ず型を拵えておいて、それへ両作家をたたき込んだ感があるから」
(元は石田憲次『漱石先生の談片』、大正6、2、1、『英語青年』)
(昭和42年の岩波漱石全集第16巻、p.722)
この書『人及芸術家としてのトルストイ並にドストイエフスキー』メレジユコーフスキーは森田草平・安倍能成訳で玄黄社から翻訳が大正3年に出ていた。本書の英訳を漱石は蔵書として持っていた。
(Merejkowski, D.H., Tolstoi as Man and Artist, with an Essay on Dostoievski, London: A. Constable & Co. 1902.)
漱石の意見ではドストエフスキーを積極的に評価していなかったように見える。ただ随筆や小説で名前を出しているくらいだから、関心はあったであろう。日記等に抜き書きをしているところからも伺える。
新潮文庫の『明暗』(昭和62年)の解説を見たら、柄谷行人(文芸評論家)が、登場人物の小林をドストエフスキー的といい、『明暗』をドストエフスキー的と呼ぶならその理解の仕方を書いている。こういう見解が大勢なのか知らない。
漱石は近代文学で最もよく読まれている小説家だろうし、ドストエフスキーとの関係の研究も多くあるのだろう。
ところで加賀乙彦『小説家が読むドストエフスキー』集英社新書、2006年を読み返していたら次のような文があり、正直驚いた。
「夏目漱石はドストエフスキーをよく読んでいました。漱石文庫にある所蔵本のなかのドストエフスキーにはたくさんの書き込みがある。まあ、漱石はすべて英語で読んだらしいですが、ドストエフスキーが大好きだった。」(同書、p.18~19)
この前には有名な『死の家の記録』の入浴場面を借りて、漱石は『吾輩は猫である』の入浴の場面を書いたのではないかとある。
漱石の蔵書は東北大学のサイトで検索可能である。そこで捜しても上記メレジュコフスキー以外なさそうである。自分の理解とずれていたが、積極的にどうこう言える知識もないので、ともかく同書でそう言っていると記しておく。
ここで参照した岩波の漱石全集も没後50周年記念の出版物であり、現在百周年の全集が刊行中である。この50年間に漱石の新たな発見や研究があっただろうから、現在の全集ならより情報が得られたかもしれない。
漱石全集からの引用は旧字、旧かなを新字、新かなに変えた。
森鴎外(文久2年〜大正11年、1862〜1922)
漱石と並ぶ我が国近代文学の巨峰、鴎外であるが、ドストエフスキー好きにとってはそれ以上の意味がある。何しろドストエフスキーの翻訳者の一人なのである。
『鰐』(1865年)を明治45年(1912)に独訳から翻訳しているのである。
であるから鴎外がドストエフスキーをどう評価していたかに加え、なぜ『鰐』を翻訳したのか、が関心となる。
残念ながら自分の調べた限りでは、なぜ『鰐』の翻訳を思い立ったかは不明である。鴎外全集の解説をみてもその辺は書いていない。
鴎外の『鰐』は青空文庫に入っていてインターネットで読める。そこの注にもあるように独訳の全集が原本のようで、他の作品も読んでいたはずだから、『鰐』しか目にする機会がなかったから訳したわけでもなさそうである。
それでは『鰐』から離れて、鴎外はドストエフスキーについてどう言っているか。
鴎外はトルストイ(1828〜1910)に関しては結構いろいろ書いている。何しろ当時は日本でもトルストイの方が評価されていたし、トルストイは鴎外が48歳の時まで生きていたから同時代人である。ドストエフスキーは鴎外が19歳、大学卒業の年に死んでいるから過去の人である。
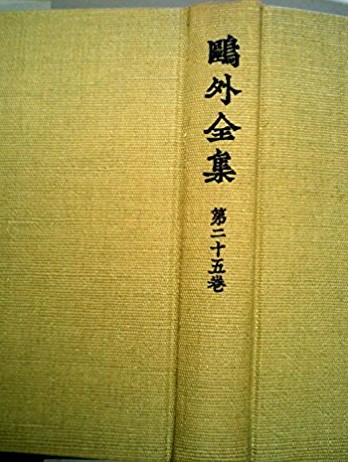 鴎外は『トルストイ』と題する論を明治32年(1899)に発表している。そこにドストエフスキーも出てくる。
鴎外は『トルストイ』と題する論を明治32年(1899)に発表している。そこにドストエフスキーも出てくる。
まずロシヤ文学について概観している。
レールモントフ、プーシキンは西欧文学の支流である。ゴーゴリは外国人が顧みない。ツルゲーネフ、ドストエフスキー、トルストイの三家が出た。ツルゲーネフは半分フランス人で半分ロシヤ人である。完全なロシヤ人はドストエフスキーとトルストイのみ。
続いて次のように述べる。
「魯西亜はいかなる国ぞ。Dostojewskyを読めば、此国の少年界を覗うべし。神を敬せず、人に服せずして、却りて又破廉恥没道徳に堕ちず。疑を懐いて自ら責め、岐に臨みて徒に哭す。人々天堂地獄の分かるゝ所の地に立ちて、犯罪の芽蘖は茲に伏せり。Dostojewskyの詩は犯罪の心理なり。知らず、此種の発酵は果していかなる酒をか成す。」
(鴎外全集第25巻、岩波書店、昭和48年、p.105、旧かなは新に、一部漢字を変えた)
文語であるし、「芽蘖」のようなまず見ない字もある(芽のこと、蘖はひこばえ)が、大体意味はわかるだろう。
続いてトルストイを読めば、ロシヤの全社会はわかるとあり、以下はトルストイ論になる。
時間は前後するが、明治30年刊行の『観潮楼偶記』にも「劇としての罪と罰と」という記事でドストエフスキーの名が出てくる。
「ドストエウスキイの罪と罰とゝ題したる小説は心理上よりおもしろきものなるを、ある人戯曲に作りかえて、伯林なるレッシング座にて興行せしめき。貧諸生ラスコルニコフが金かしの婆を殺すところは、世の常の強盗の所為になり、ラスコルニコフにおもわるゝ私窩児ソニヤが事は工女に作りかえられて、世の常の恋になりぬ。」
(鴎外全集第22巻、岩波書店、昭和48年、p.530、旧かなは新に変えた)
私窩児なんて言葉知らなかった。私娼のことか。
『罪と罰』は「心理上よりおもしろきものなる」が鴎外の評価か。この文の初出は明治25年だそうである。(同書p.627の解説)
『椋鳥通信』にもドストエフスキーの名がみえる。「椋鳥通信」とは明治の終わり頃に雑誌「昴」上に連載した、海外事情ニュースである。もちろん日本にいたわけだが、海外のニュースをいち早く入手し、鴎外の関心により様々な情報、三面記事的なものから文芸上の出来事等々、を載せている。
ドストエフスキーの名は何度か出てくる。仏教を論じたところで、
「Dostojewskiの「Karamasow兄弟」を見ると、ロシアの寺院生活がどの位仏教臭いか分かる。」
(1911,7,30発、鴎外全集第27巻、岩波書店、昭和49年、p.567)
とある。鴎外はカラマーゾフを読んでいたとわかる。
あとは大したものはなくて、例のヴォギュエが死んだ時に「トルストイやドストエウスキイをフランスに紹介した人である。」(同書p.196)とか、ゴーリキーの文にシベリヤに誰それが流されドストエフスキーが帰って来た、などである。
なお岩波文庫に池内紀編「椋鳥通信」上中下の三巻があるが、全部ではないのでドストエフスキーの部分は収録されていないようである。
『森鴎外とドストエフスキイ』(西山邦彦著、1980年、啓文社)という本があるが、鴎外とドストエフスキーをそれぞれ論じていて、また半分は『悪霊』論であり、ここでの関心とは離れている。
ところで岩波の鴎外全集の、「椋鳥通信」の入っている巻は感心しない。以下は脱線だから読む必要はない。
大部で929ページもあるのに、目次は椋鳥通信とあるだけ。各ページの肩も椋鳥通信としかない。解説に雑誌の何年何月何日発という一覧はあるのに、ページを開いてもそれが何年の何月何日分か分からないのである。ページをめくって文の終わりに、何月何日発と書いてある所を見つけ出さなくてはならないのである。さすがに岩波文庫の目次はもう少しまともである。
全集には(岩波文庫も)人名索引はある。しかしそこにドストエフスキーはない。あまり重要でないからであろう。索引の充実は望まれるが大変な作業であるとわかる。
しかしこんなことは今ならもっと簡単にできるのである。電子書籍化すればよいのである。キーワードを入れて検索すれば一発である。索引なぞ要らなくなる。
紙の本と電子書籍を対立させ、情緒的に電子書籍に反発しているような文を見かけるが、このような人は、漫然と小説を最初のページから読むような接し方しかしていないのであろう。紙の本と電子書籍は夫々特徴があり、ともに必要なのである。
(続く)
ドストエフスキー全体のトップへ
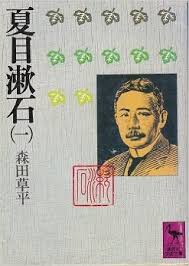

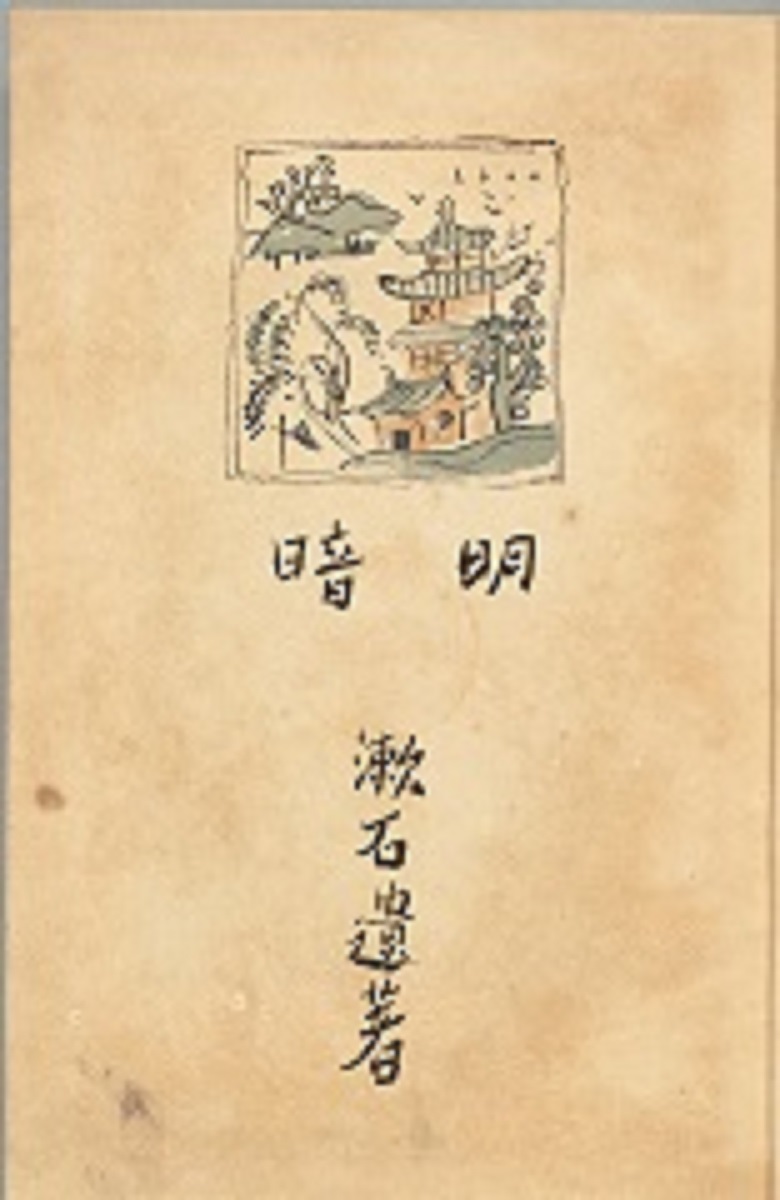
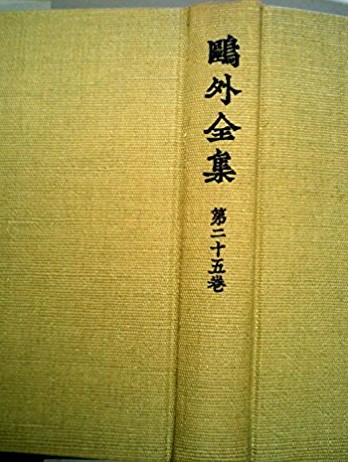 鴎外は『トルストイ』と題する論を明治32年(1899)に発表している。そこにドストエフスキーも出てくる。
鴎外は『トルストイ』と題する論を明治32年(1899)に発表している。そこにドストエフスキーも出てくる。