
松下裕訳、筑摩叢書、上巻昭和48年、282頁、950円(昭和50年2刷)下巻昭和49年、330頁、1,300円(昭和54年2刷)
2度目の夫人、アンナがドストエフスキーとの生活の記録をつづったもの。
アンナは1918年に71歳で亡くなった。遺稿の本書をグロスマンが編集して1925年に出版された。その後新たに編集されたものが1972年以降の全集に収録された。
作家自身の著作以外では第一に読むべき本であろう。
最も身近な観察者による文豪の生活の記述である。アンナが良く夫を観察していることがわかる。評論家等が書く、作家に関する日常的な解説は大体この回想からの引用である。もちろん文豪亡き後、未亡人がかつての夫を描いたものであるから、評価の「中立性」は甚だ怪しい。
しかし妻という立場でなければ知りえない事実や文豪の生活態度が伺えて、人間ドストエフスキーがわかる。
現在ではみすず書房から刊行。
高見裕之訳、アカギ書房、昭和21年、255頁、25円、アンドレ・シュアレスによる序
原著は1920年、フランス語で発表された。
作家の次女リュボフィ(1869年〜1926年)が書いた父の回想。リュボフィはロシア語で「愛」という意味である。革命後フランスへ亡命した後はフランス語風に変えて使った。
この作者リュボフィと回想の評価については、新潮社版ドストエフスキー全集第23巻「妻アンナとの往復書簡」(1980年)の訳者木村浩がその解説に簡単に書いてある。若干引用すると、
「母親と折り合いが悪かったエーメは、母親の死に際してもロシアへは戻らず、その一年後にこの「回想」を書きあげたようにみえる。この本はその後ドイツ語訳も出版され、一時は世界的にかなり読まれたようだが(わが国でも独語からの翻訳が大正十二年(1923)に出版されている)が、今は一部の記述に事実と相違するものがあることが指摘されている。」
(同書p.479〜480)
この古い本の訳者後記を見ると仏語からの訳で、上で木村浩が言及している大正時代の訳の復刻ではない。
事実との相違点を記した上で、新訳を出して欲しいものだ。

水野忠夫訳、河出書房、1966(昭和41年)、443+18頁、800円
題名とおりドストエフスキーを身近に知っていた身内、友人等がドストエフスキーについて書いた回想をまとめたもの。
内容:
■幼年・少年・青年
アンドレイ・ドストエフスキー
コンスタンチン・トルトフスキー
アレクサンドル・リーッゼンカンプ
■作家の誕生
ドミートリイ・グリゴローヴィッチ
アブドーチャ・パナーエワ
ウラジミール・ソログープ
ステパン・ヤノフスキー
■流刑地にて
アレクサンドル・ミュリコフ
ピョートル・マルチヤノフ
アレクサンドル・ウランゲリ
■再出発
ニコライ・ストラホフ
ニコライ・チェルヌイシェフスキー
ソフィヤ・コワレフスカヤ
■結婚
アンナ・ドストエフスカヤ 回想
アンナ・ドストエフスカヤ 日記
■晩年・死
フセボーロド・ソロビョフ
ウラジミール・コロレンコ
グレープ・ウスペンスキー
アンナ・ドストエフスカヤ
アレクセイ・スボーリン
他に年譜、解説、索引
なお、同時代の回想としては筑摩版ドストエフスキー全集の別巻にも何人かの文が入っている。

中村健之介訳、みすず書房、1989年、316頁、2,472円
ドストエフスキーの愛人として知られる「魔性の女」スースロワの日記(1863年8月以降)である。
編者ドリーニンの解説のほか、スースロワが書いた小説『他人と身内』、ドストエフスキーと交換した手紙、訳者解説が収録されている。
アポリナーリヤ・プロコーフィエヴナ・スースロワ(1840年生まれ)とドストエフスキーとの仲は1862年より始まっているようである。
ドストエフスキーの2回目のヨーロッパ旅行は1863年8月から始まる。パリでスースロワに会う。既にスースロワの心はドストエフスキーから離れ、スペイン人の医学生サルヴァドールに移っていた。スースロワの心変わりを知り、情けない様子のドストエフスキーとの会話が日記にある。スースロワにしても相手のスペイン人には、つれなくされていた。スースロワが好きなドストエフスキーはその後も尽くすつもりでいた。9月になって二人でイタリアに旅行する。10月初めにスースロワと別れるので、その後の日記は長い間ドストエフスキーは登場しない。1864年の2月に、なぜドストエフスキーと結婚しないかと聞かれ、したくないからと答えている。(p.188)
1865年11月にペテルブルグでドストエフスキーに会い、口論になる。(p.208)ずっと前からドストエフスキーは求婚しているが、スースロワを苛立たせるばかりだ。ドストエフスキーが嫌みを言うので怒る。
『他人と身内』はドストエフスキーとスースロワの関係を基にした小説である。男が女を訪ね、女が他の男を愛していると知り、絶望し怒る。女も相手の男から捨てられた。二人はフランスに行く。
全く事実を基にスースロワが作り上げた小説である。
日記はかなりの部分にドストエフスキーは出ず、読んでいてそれほど面白いわけでない。ただしドストエフスキーの小説に登場する、多くの女の造形に影響を与えたスースロワという女が分かる。またドストエフスキーの関係も小説内の男たちの行動に映されている。

ツヴァイク全集第8巻、みすず書房、昭和49年
三人の巨匠とは、バルザック、ディケンズ、ドストエフスキーのことである。これら19世紀を代表する長編作家について夫々論じている。
ツワイクは伝記小説作家として有名である。最も有名なのは『マリー・アントワネット』であろうか。なんとかのバラという一時有名だった少女漫画の下敷きにも使われた。
その他『ジョゼフ・フーシェ』『メアリー・スチュアート』も忘れがたい印象を残す。さらにこの人の短編小説を読んでいると、まるで戦前のヨーロッパ映画を観ているような気分になる。個人的には若い時に読んだ『ジョゼフ・フーシェ』(潮文庫版)が特に思い出が深い。
閑話休題。このツワイクのドストエフスキー論は他のあまたの論と一線を画す。ドストエフスキーについて論じると、例えば書簡や近親者の回想から適当に抜書きし、後は具体的な個々の作品を論じてページを稼ぐといったものが多い。
それに対してこのツワイクの文はドストエフスキーの特徴について延々と一般論を170ページも続けるのである。登場人物や作品は必要に応じてひっぱてくるだけである。
そこで述べられている意見は特段目新しいものではない。我々のイメージと変わらない作家像であるが、事実の正確さなどはあまり気にせず情熱的とも言える筆致で綴っていく。
例として有名なプーシキン記念祭の講演の模様では次のようにツワイクは述べる。
プーシキン生誕百年祭に、ロシヤの名だたる作家たちが、記念講演をするために招かれた。西欧主義者で、一生涯ドストエフスキーから名声を横取りしていた作家ツルゲーネフが皮切りを受けもち、おだやかな好意的な善意に包まれて講演をおわる。その翌日がドストエフスキーの講演である。彼はデーモンの陶酔にひたりながら、言葉をまるで雷の楔(くさび)のようにつかんでは投げつけた。低くかすれたような声で話しながら、とつぜん雷鳴がとどろき、陶酔の炎が燃え立つといったような話しかたで、ロシヤが全世界に対してもつ和解的使命について告知をなした。聴衆は薙ぎ倒されたように彼の膝元へひれ伏した。会場は歓呼の爆発のために震動し、女たちは彼の手に接吻し、一人の大学生は彼のまえで気をうしなって倒れ、そのあとに予定されていた講演者たちは皆、講演をあきらめた。感激はきわまりなく高まるばかりであり、いばらの冠をかぶった彼の頭の上には栄光の炎が燦然と燃えさかった。
(ツヴァイク全集第8巻、p.123、神品好夫訳)
実際プーシキン祭のドストエフスキー講演は熱狂的であったそうだ。(書簡の1880年6月8日アンナ宛)
しかしその熱狂ぶりを客観的に記そうとするのが他の伝記作者であるが、ツワイクでは自らも興奮して感情移入しているところが面白い。

中山元訳、光文社古典新訳文庫、2011
高橋義孝訳、フロイト著作集第3巻所収、人文書院、昭和44年
精神分析の創始者に止まらずその後の思想哲学に多大な影響を及ぼした、フロイトによるドストエフスキー論。
エディプス・コンプレックスを父親殺しとの関係で論じている。
事実認識については執筆当時の制約がある。現在ならもっと説得的な分析ができるかもしれないが、それを超えた巨人による巨人論として読むべき論文。
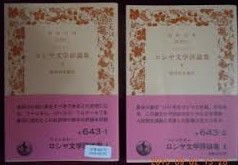
除村吉太郎訳、岩波文庫I、1950年、254頁、450円(1988年第10刷)
II、1951年、220頁、400円(1988年第9刷)
1830〜40年代の有力評論家ベリンスキーの評論集。
ドストエフスキーがこの評論家の激賞によって世に出たことは有名であろう。また続く作品群を全く評価しなかったことも。実際の当時のベリンスキーの評が読める。
2冊のうちIには『ペテルブルグ文集』『1846年のロシヤ文学観』(共に1846年)、IIには『1847年のロシヤ文学観』(1847)が収められている。
『ペテルブルグ文集』ではプーシキン、ゴーゴリ、レールモントフに触れた後『貧しき人々』の作家の賞賛が続く。
58ページ以下で『二重人格』(『分身』)の評が始まる。ややためらいがちに言葉を選んでいる。『1846年のロシヤ文学観』ではずばり言っている。
「もしドストエフスキー氏が自分の「二重人格」を少なくとも三分の一だけちぢめたとしたら、この小説は成功したはずだ、とわれわれは信ずる。しかしその中にはまだもう一つの本質的な欠陥がある。それはこの小説の幻想的な色彩である。幻想的なものはわれわれの時代においては狂癲院のみにありうるので、文学にはありえない。そして医師の管理に属しうるので、詩人のそれには属しえない。」(p.167〜168)
ベリンスキーは冗長さと幻想的色彩を攻撃し、リアリズムしか受け入れられなかったようである。
『プロハルチン氏』も「あんなわざとらしい、気取った、わけのわからない、そして詩的作品というよりはむしろ、何か本当の、しかし奇妙でこんがらがった出来事に似たもの」(p.168)とこき下ろす。
IIには『1847年のロシヤ文学観』が収められ、ドストエフスキーでは「女主人」(『家主の妻』)が取り上げられている。
「これはきわめて注目すべきものであるが、しかしただわれわれがいままでかたった諸作のような意味においてではけっしてない。もしこの小説になにかの知られざる名前が署名してあったとしたら、われわれはそれについて一言もかたらなかったであろう。」(p.150)
「この中篇全部に一つの平明な、そして生きたことばあるいは表現もない。--すべては凝っており、わざとらしく、おおげさであり、偽造的、にせもの的である。(中略)これはなんだろう? 奇妙な作である! わけのわからない作である!」(p.152)
ベリンスキーは『貧しき人々』を絶賛したことを悔いていて、反動でボロクソ言っているのかと思いたくなる。
これらの評価は現代のそれと違うだろう。しかし新進作家時代のドストエフスキーが目にした論評なのである。
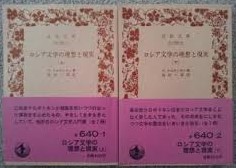
高杉一郎訳、岩波文庫、(上、1984年)、(下、1985年、300+17頁、500円)
革命家のクロポトキンによるロシヤ文学史である。原著は1905年に第1版が出て、1916年に第2版が出ている。各章の題名は次の通り。
第1章序説
第2章プーシキンとレールモントフ
第3章ゴーゴリ
第4章トゥルゲーネフとトルストイ
第5章ゴンチャローフ、ドストエフスキイ、ネクラーソフ
第6章演劇
第7章民衆作家
第8章政治文学、風刺文学、文芸批評、その後の作家たち
となっており、20世紀初頭におけるロシヤ文学の作家の位置付けの一例であろう。
ちょっと引用しておく。第4章冒頭には次のようにある。
「ロシアの作家が西ヨーロッパに知られる障害になっていた言葉の壁をうち破ったのは、19世紀全体を通してまでと言わないにしてもロシアで最も偉大な二人の作家トゥルゲーネフとトルストイであり、いくらかはドストエフスキイでもあった」
(上巻p.160)
ここではドストエフスキーは3番目、他のところではゴンチャロフを3番目の作家ということにしている(下巻p.13)。
それにしても第5章で3人まとめて挙げられている中の一人である。ここの部分を読む限りクロポトキンはドストエフスキーをあまり高く評価しているように見えない。
「ドストエフスキイの作品をもっぱら美学的な観点からだけ判断するとすれば、その文学的価値にかんする批評家たちの評価は、すこぶるきびしいものにならないわけにはいかなかったであろう。」(下巻p.40)
「「カラマゾフの兄弟」はドストエフスキイのすべての作品のうちでいちばん芸術的に完成された作品であるが、同時にそれは作品の精神と創造力の内的欠陥をあますことなく暴露されている小説である。」(同p.46)
「ドストエフスキイの小説の芸術は、トルストイ、トゥルゲーネフ、ゴンチャローフというロシアの三大巨匠のそれよりもはるかに劣る。
ドストエフスキイの小説、とくに後期の作品の登場人物はすべてなにかの精神病や道徳的倒錯をわずらっている人間ばかりということである。」(同p.48)
本書の見解が当時の支配的意見かどうか不明だが、このような評価もあろう。

小笠原豊樹訳、河出文庫、2013年、311頁、1,200円
『ロリータ』の著者ウラジミール・ナボコフによるロシヤ文学論。
上巻ではゴーゴリ、ツルゲーネフ、ドストエフスキーが、下巻ではトルストイ、チェーホフ、ゴーリキーが扱われる。
1899年ペテルブルグに生まれたナボコフは1940年アメリカに渡る。20世紀を代表する小説の一『ロリータ』が書かれる50年代半ばまで、大学で文学の講義をしていた。ドストエフスキー論はその際の講義録だそうだ。
ドストエフスキーの所では作家の生涯や一般論を述べた後、具体的作品として『罪と罰』『ねずみ穴から出た回想記』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』を取り上げる。
『ねずみ穴から出た回想記』とはなんだと思うが『地下室の手記』のことで、こちらの方が正しい意味だそうだ。
ナボコフはドストエフスキーを高く評価していない。以下、いくつかの引用と要約。
他の真に偉大な作家(トルストイ等)と比べれば、ドストエフスキーはむしろ凡庸な作家という。彼は読者の側に同情を引き起こそうと、ありふれた感情を非芸術的に誇張する感傷的な作家とされる。(p.227,p.236)
ナボコフはドストエフスキーの作品のうち『分身』を最良とする。(p.238)
ドストエフスキーはロシヤ最大の劇作家となる運命だったのに間違って小説家になった。劇の方がドストエフスキーに向いているというのである。(p.239)
主要人物の中に多くの精神病質者がいる。彼の登場人物には性格の展開が見られない。ラスコーリニコフでさえ外側から起こる出来事によって調和の方向へ至る。(p.248)
ナボコフは『罪と罰』を12歳の時、初めて読み感動したようだが、19歳の再読では感傷的な悪文と思い、その後読み直しを続けこの作品の間違いを悟ったそうである。(p.250)
「堕落の喜びというのはドストエフスキーの大好きな主題の一つである。」(p.261)
「ドストエフスキーはこの作品でも他の作品でも、十八世紀の喜劇のように、人物に説明的な名前をつける傾向がある。」(p.271)これは江川卓によって我々も知った。
「この作家には喜劇と悲劇を混ぜ合わせるすばらしい才能があった。一流のユーモリストと、この作家を呼ぶこともできよう。」(p.273)
『白痴』のナスターシャは「ドストエフスキーの小説ではよくお目にかかる、例のちょっとやそっとでは受け入れ不可能なほど非現実的な、読者を苛立たせる人物の一人である。」(p.284)
「ドストエフスキーの得意の主題をかたちづくるのは人間の尊厳が蒙る災難ということ」(p.290)
作家の理解、評価は人によって異なり、一つの正しい解釈があるわけではない。
ドストエフスキーは劇作家になるべきであったとか面白い。彼はユーモリストだ、は最近日本でも流行っているようだが。
ドストエフスキー論は大抵興味がわかず読み進められないが、このナボコフの本は面白く読めた。
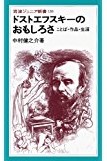
ロシア文学者、元東大教授、ドストエフスキー関連の著書を多く出している。
岩波ジュニア新書、1988、195+13頁、780円
作家の著作の中から文を引用し、見開き2頁でそれにを元にドストエフスキーについての情報や著者の考えを書いており、読みやすく勉強になる。
名言集の好きな人には勧められる。

集英社新書、2006年、217頁、680円
ドストエフスキーの小説について語った講演をまとめたものなので読みやすい。取り上げられている作品は『死の家の記録』『罪と罰』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』である。
題名のとおり小説家と言う立場から、即ち創作する側からドストエフスキーの作品を評価しているところが新鮮であり、価値がある。またキリスト教的な読み方、評価の必要性を説く。
気になった点は次の通り。ドストエフスキーはニーチェの影響を受けている、というのである。逆の、ニーチェのドストエフスキーへの言及なら誰でも知っているだろうが。
「ドストエフスキーはニーチェの熱烈な読者でもあった。」(同書、p.137)
「彼(キリーロフ)が死ぬのは「超人」になるためです。もちろん、この「超人」はニーチェの言葉です。」(同書、p.143)
「(前略)ドストエフスキーもニーチェからの引用というか、ニーチェの影響を大きく受けていて、(後略)」(同書、p.199)
ドストエフスキー(1821~1881)よりニーチェ(1844~1900)は20歳以上年下で、ニーチェの主要著作の多くはドストエフスキーの死後出された。超人の出てくるツァラトゥストラは1885年の出版である。
更に細かい話をすると、成長して革命集団を作るというカラマーゾフの第二部の構想は「創作ノートのなかにはかなり詳しく、筋書きを含めて書いてあります。」(同書、p.206)とあるが、創作ノートにはそんなことは書いていない。
気になった点を列挙したが、揚げ足取りのつもりでなく、全体として見れば本書の価値を損なうものでない。
著者は精神医出身の小説家(作品に『宣告』など)。
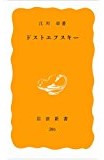
岩波新書、1984、212+4頁、430円
なんでも江川卓は今めっぽう有名で人気らしい。この本のamazonの読者書評欄で「日本で、ドストエフスキーといったら、すぐ連想されるのが彼ではないでしょうか」とありびっくりした。ドストエフスキーなら米川正夫ではないかというのは古い世代らしい。
この人長編でも『白痴』や『未成年』は翻訳していないはずだし。『謎とき罪と罰』(新潮社、昭和61年)及びそれに続く謎解きシリーズのせいだろうか。
この新書版でも謎解きシリーズ同様、ロシヤ語では、ロシヤの文化、習慣によれば、ここではこうドストエフスキーは意図していたのだ、と謎解きをしてくれる。
読んでいて面白いのは確か。我々ロシヤ語やロシヤの文化に無知なものはこれを読んで初めて知る事柄でも、ロシヤ人ならわかるらしいので、随分ドストエフスキーへの印象が異なるのでないか。
また日本語なら知っているので、ここでの手法は日本文学の評論に適用できるかもれない。
江川本を読んでいると、ドストエフスキーの『作家の日記』1873年第4号にある、短編『鰐』についての解釈に対する作家自身の反論を想い出してしまう。つまり作家の書いた『鰐』は、同時代の作家チェルヌイシェーフスキーが逮捕された事件を戯画しているのだ、と批判された。これに対してドストエフスキーは怒って反論している。
つまり完全なこじつけだと。そのつもりならなんでもこじつけが可能と見栄を切っている。
江川の所論をこじつけと言うつもりはない。判定する能力もない。しかしこれを思い出してしまったことは確か。
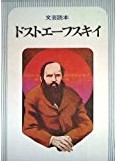
河出書房、昭和51年、328頁、定価680円
ドストエフスキー論で特に著名なもののエッセンスをまとめてあり、便利である。
日本人としては、小林秀雄、秋山駿、椎名麟三、森有正、河上徹太郎、西谷啓治ほか。
外国人では、シェストフ、ベルジャーエフ、ジィド、カーの論考、及び解題がある。
なおこのような古典的な論文に関しては小沼訳ドストエフスキー全集の別巻にも所収。
埴谷雄高と大江健三郎の対談、『白夜』『大審問官』の訳。
巻末に文豪の年譜の他、「ドストエーフスキイ文献」(近田友一編)があり、古い文献が出ていて便利。
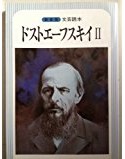
河出書房、昭和53年、264頁、定価680円
ドストエフスキー読本の続編である。
日本人では、埴谷雄高、寺田透、大岡昇平、後藤明生、阿部六郎その他。
外国人では、オーザノフ、マリ、バフチン。
「ドストエーフスキイ文献」の続編も掲載。文献については発行時期以降の補足が必要となろう。

村上香住子訳、中公文庫、昭和63年、736頁、860円
文庫なので、作家の生涯及び主な作品について気楽に接することができる伝記。
もっとも736ページあり、それなりの量があるが下記モチューリスキー本に比べればたいしたことない。
著者はロシア生まれでフランスへ亡命した作家(1911〜)。原本の初版は1940年。
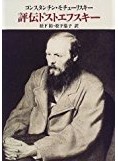
松下裕、松下恭子訳、筑摩書房、2000年、754頁、8,800円
内容はドストエフスキー論、ドストエフスキーの作品論が主で、伝記も一緒に記述されている本である。
大部なので詳しく各作品を論じてある。本書を読めばドストエフスキーの小説のあらましとその解釈の例が分かる。解釈は標準的、基礎的である。ドストエフスキー論を読みたければ、まず勧めてよい本である。
ただ大部なので値段が高く、全体を読むには時間がかかる。
著者コンスタンチン・モチェーリスキー(1892~1948)はロシヤ生まれの文学史家。1919年亡命しパリで大学教授をつとめた。本書は1942年執筆、1947年に2部で出版、1980年合本出版。
北垣信行訳、筑摩書房、昭和41年、430頁、1,800円。冒頭に4頁の白黒写真、菊判二段組。
ソ連時代のドストエフスキー研究家、レオニード・グロスマン(1888~1965)による伝記。1963年に初版が出、改訂版が1965年に出版されている。
第一次資料の駆使やアンナ未亡人への聞き取りを基にした伝記で長く読まれてきた。書中の評価に関してはソ連時代の制約がある。また本書後、明らかになった事実もあると思われる。ただし読みやすい伝記である。
本書は装丁を変え、昭和53年に再刊されているが、中身は同じ。
なお新潮社版全集の別巻「年譜(伝記、日付と資料)L・グロスマン」1980年は、1935年に出版された別の書籍。グロスマンの原著に訳編者の松浦健三が追加、削除等行なった、詳細な年譜である。

集英社、昭和46年、p.371+関連年表、1,900円
ペトラシェフスキー事件に関係する資料、論稿の集大成。目次は次の通り。括弧内は著者。
「デカブリストからペトラシェフスキー会まで」(原卓也)/「評伝 ペトラシェフスキー」(原卓也)/「聖なる人間」(エンゲリソン)/「法律気ちがいの男」(バクーニン)/「ペトラシェフスキー会員のこと」(ドストエフスキー)/「魂の深みで詩が生まれたとき」(シャンスキー)/「兵士の話」(グリゴーリエフ)/「三十五年前のこと」(アフシャルーモフ)/「ドゥロフ・サークルのこと」(ミリュコフ)/「激しやすい人たちの中で」(ミルレル)/「ベリンスキーとゴーゴリの往復書簡」(ベリンスキー、ゴーゴリ)/「十戒」(フィリッポフ)/「知的活動への愛着」(ヤノーフスキー)/「秘密印刷所」(アポロン・マイコフ)/「秘密印刷所のこと」(クトゥーゾフ)/「現代的欺瞞の一つ」(ドストエフスキー)/「ペトラシェフスキー事件覚書」(リヴォフ)/「秘密結社のこと」(スペシネフ)/「フーリエ誕生日の演説」(アフシャルーモフ)/「密偵者の報告」(アントネルリ)/「担当官の見解」(リプランディ)/「アレクセーエフ半月堡のドストエフスキー」(ベリチコフ)/「獄中からの書簡」(ドストエフスキー)/「ドストエフスキーの供述書」(原卓也)/「ドストエフスキーに対する人定訊問」(原卓也)/「ドストエフスキーの個々の供述」(原卓也)/「逮捕から裁判まで」(ヤストルジェムブスキー)/「処刑場の回想」(アフシャルーモフ)/「政治犯と流刑」(原卓也)/「ドストエフスキー逮捕からオムスク要塞まで」(小泉猛)/「流刑地からの書簡」(ドストエフスキー)/「あとがき」(原卓也)

北海道大学出版会、1993年、515頁、4,800円
若き日のドストエフスキーがペトラシェフスキー事件によって逮捕された際の裁判関連の記録を集成したもの。
目次は以下の通り。
解説…中村健之介/秘密警察「第三課」の、ドストエフスキー逮捕命令/逮捕の朝/ペトラシェフスキーの「金曜会」出席者名簿からの抜粋/予備審問に対するドストエフスキーの釈明書/ドストエフスキーが所蔵した本についての文書調査委員会の報告書/ドストエフスキーの退役証明書とゴリーツィン公爵の送り状/諜報員アントネリーの報告/証人たちの証言/被告人の供述/ドストエフスキーに対する人定訊問/公式審問に対するドストエフスキーの供述/他の事件関係者についての記録に含まれているドストエフスキーの供述/アポロン・マイコフの手紙と談話/退役工兵中尉ドストエフスキーに関する記録抜粋/退役工兵中尉ドストエフスキーに関する軍法会議の決定/軍法会議におけるドストエフスキーの宣誓書/法廷における陳述/判決/最高軍法会議の決定と皇帝の裁可/兄ミハイル宛の手紙...死刑執行の日/ドストエフスキーの護送に関する命令/ドストエフスキーの護送出発の報告/名簿/原編者による解説…N・F・ベリチコフ/訳者あとがき/人名索引
ドストエフスキー自身の証言は、原卓也・小泉猛編訳『ドストエフスキーとペトラシェフスキー事件』や新潮社版全集第24巻に「裁判記録」として載っているが、ここでは警察側の記録など事件全体を把握するための資料が揃っている。
また訳者中村健之介による解説や詳細な注がついている。
ペトラシェフスキー事件はシベリア流刑をもたらしただけでなく、この際の経験が後年の文豪の文学に決定的な影響を与えたことは知るとおり。
この事件の裁判について詳細な情報を得たい向きには役に立つ資料集である。
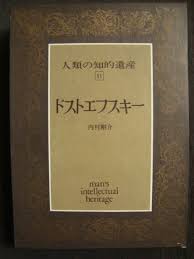
昭和53年、講談社、381頁、1,500円(昭和53年2刷)
これが含まれている全集は、古今東西の代表的思想家、哲学者をとりあげ、その思想の紹介や主な著書の部分を訳し解説をしようとするもので全80巻出された。
思想家ドストエフスキーとして選ばれている。中公の「世界の名著」のようなもので、原典の訳より解説が主となった全集という感じ。対象は「世界の名著」と同じ思想家が多いが、トルストイや、その他多くの非西洋の思想家も選ばれている。
本書の特色として『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」の冒頭近くに出てくる『聖母の地獄めぐり』が訳載されているのが他にない利点。
更にロシヤ・ソビエト、フランス、イギリス、ドイツ、日本におけるドストエフスキーの受容が簡潔にまとめられているところも便利である。
書中の「肉声抄」はドストエフスキーの名言集として詳細なもの。
内村剛介はロシヤ文学者、北大教授(当時)。
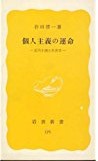
岩波新書、202頁、1981年、380円
著者は社会学者、京大教授等を勤めた。
ジラールの「欲望の三角形」という図式で文学を論じる。”主体 ― 媒介者 ― 客体”の三角関係を意味する。主体とは本人あるいは特定の個人、客体は欲望の対象、例えば恋人でも名声でも良い、主体にとって価値があるもの。媒介者は、主体にとって優位にあるライバルであり、客体(欲望の対象)を手に入れている、そういう意味で尊敬と憎悪の相反する(ambivalent)感情を主体は持つ。
『悪霊』で言えば、主体をピョートル、シャートフ、キリーロフとすれば、スタヴローギンが媒介者である。
このような仕方でドストエフスキーの作品、永遠の夫、地下室、カラマーゾフ等を初め、他の作家も論じていく。ドストエフスキー理解の一方法として一読の価値はある。
なお、著者は別に『ドストエフスキーの世界』1988年、筑摩書房がある。こちらの方がドストエフスキー論として優先すべきであろうが未読であり、より身近な新書を挙げた。
創文社、昭和36年、1,023頁、3,800円
著者は元京大教授、専門は政治思想史。
副題にあるように西欧主義とスラブ主義の対決という観点からロシヤの政治思想を論じる。第一部から第三部まで分かれる。
第二部で西欧派の思想家を取り上げる。ベリンスキー、バクーニン、ゲルツェンである。
第三部でスラブ主義の思想家。キレエーフスキー、ホイヤーコフ、ダニレフスキー、ドストエフスキーである。
正直言って西欧派の諸氏は有名であるのに対し、スラブ派はほとんど知らない。ドストエフスキーは最終章の第15章で「ドストイェフスキーにおけるスラブ主義の甦生」という題で充てている。
人間学、自由の弁証法、大審問官、個人と社会、ナロードなどを手掛かりに作家論じている。
昔、古本屋で本書を見た時はそのあまりの大きさ(厚さ)に驚いたものである。今入手してみると先入観のせいかそれほどでもない。しかしこれだけ厚い本はざらにない。

岩波文庫(下)、西川正身訳、1997年、349頁、660円
文庫は上下2冊に分かれており、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は下巻に載っている。原著は1954年刊。
ちなみに選ばれている十大小説は『トム・ジョーンズ』『高慢と偏見』『赤と黒』『ゴリオ爺さん』『デイヴィッド・コパーフィールド』
『ボヴァリー夫人』『モウビー・ディック』『嵐が丘』『カラマーゾフの兄弟』『戦争と平和』である。
まずドストエフスキーの生涯について結構詳しく説明する。本人の書簡の引用だけでなく、例のストラーホフのトルストイあての、ドストエフスキーの異常事を語った手紙まで紹介している。もっともモームは文豪を弁護している。
「彼の描く人物がまるでありそうになく、またその行動の動機が馬鹿らしいほど取るに足らないもののように思えるのである。」(下p.222)
モームによれば小説を構成するには、首尾一貫した、全体を完全なものするため論理的な精神が必要である。ところがドストエフスキーはそういった才能がなく、しかし個々の場面でサスペンスを作り出し、劇的なものにする天賦の才は驚くべきと言う。
読者の感受性を刺激するためドストエフスキーが用いる手は次のようだと言う。
「彼が描く人物は、それぞれが口にする言葉と釣り合いがとれぬほど興奮する。お互いに相手を侮辱する。突然わっと泣き出す。顔を赤らめる。顔色が青ざめる。さらには恐ろしいまでに蒼白となる。そして何でもないごく普通の言葉にも、読者には容易に説明のつかない意味が付せられているので、いま言ったような常軌を逸した挙動や病的な感情の爆発に接して、読者は次第に興奮をおぼえ、ついには神経が極度に高ぶってきて、そうでなければ、ほとんど心に動揺をおぼえないでしまうようなことが起こっても、容易に心底から衝撃を感じてしまうのである。」(下p.225〜226)
モームはカラマーゾフを十大小説の一に選んでいるわけだから評価しているのである。ただ冷静に分析している。
作家論に詳しくないのだが、日本のドストエフスキー論は基本的にドストエフスキー信者しか書かないのではないか。だから「余は如何にしてド氏信徒となりし乎」とか、教祖の作品の魅力、意図を語るといったものが多いのではないか。少なくともインターネットで目にするのは。あるいは逆に「自分は大勢に流されない、大して傑作でもない」と粋がって、格好つけているつもりになっているものみたいな。
モームの論を読んでいると第三者的な解説で、変わっていて面白い。ドストエフスキーは全体を首尾一貫にする才能が欠け、個々の場面を劇的なものとする才は驚くべき、とはナボコフの言うむしろ劇作家に向いていた、と通じるものがあるか。

中公文庫(下)、中村保男訳、2012年、317頁、905円
コリン・ウィルソンと言えば、殺人実録ものが多い印象を受けるが、本書が処女作であり最も評価も高い。原著は1956年出版。
題名のアウトサイダー、即ち部外者、疎外者、はみだし者は以下の意味を持つ。
アウトサイダーは社会(体制、主流派)から少数派であるが故に距離を置いている、その自らの立場も理解している。
しかし決して劣等感を感じるのでなく冷やかに体制を眺めている人である。
これを論じるため、多くの芸術家や思想家(ヘミングウェイ、ニーチェ、ゴッホ等)を取り上げている。
本書は哲学といってよい本であり、難解である。
ドストエフスキーは下巻で論じられている。
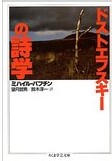
ちくま学芸文庫、望月哲男、鈴木淳一訳、1995年、602頁、1500円(2011年15刷)
あまりにも有名なミハイル・バフチンの本。翻訳の元となった第2版は1963年出版。
多分最も有名なドストエフスキー論である。誰でもポリフォニー小説、カーニバル文学という言葉は聞いているだろう。
本書は他の作家論の類と比較できるものではない。ドストエフスキーの創作方法を論じた本なのである。作品、登場人物を論じるのが主ではない。
題名の詩学とは字面からの印象とは違い「芸術の創作において題材、ジャンル・・・等の選択を支配する、作者の創作姿勢の全体を意味する」(p.10)
その創作方法が有名なポリフォニー性である。元々ポリフォニーとは音楽用語で幾つかの声部(例えばソプラノとかバスとか)が独立して、一つの主部に他が従属するとかでなく、夫々が同じ重要度を持ち進行する音楽作法である。他にモノフォニーとホモフォニーがある。
バフチンは「それぞれが独立して互いに融け合うことのないあまたの声と認識、それぞれがれっきとした価値を持つ声たちによる真のポリフォニーこそが、ドストエフスキーの小説の本質的な特徴なのである」(p.15)と述べる。「複数の対等な意識」、主要人物たちは「作者の言葉の客体であるばかりではなく、・・・自らの言葉の主体でもある」(同ページ)
「ドストエフスキーはポリフォニー小説の創造者である」とドストエフスキーがこの新しい芸術形式を始めたのだと言う。(p.16)
カーニバル文学という言葉は第4章で出てくる。カーニバル的世界感覚は古典古代以降の文学で歴史がある。現在性、経験と気ままな思いつき、複数の文体、多様な声といった特徴がある。
非常に難解な書である。ドストエフスキーの小説を難解だとか目にするが、そう思ったことはない(きちんと理解しているかどうかは別である)。本書は一文一文が何を言わんとしているかよく分からず、ともかく自分なりの理解で先に進んでも全体を読み通せるまで気力が続かなかった。本書を読んでいて感じるのは、ドストエフスキーに留まらず、文学論、文学批評全般を扱っているのかと思わせる点である。多彩な文学の引用で読者を圧倒する。批評家志望とか文学研究者志望の人を感心させるだろう。
世の中にはドストエフスキーの創作そっちのけでドストエフスキー論を追っかけている人がいる。それは個人の勝手だが、そういう人たちにとって本書は聖典視されている。
持っている本の奥付を見ると、1995年1刷で2011年に15刷までなっている。現在までなら更に売れているだろう。本当に読んでそれなりの理解をしているのだろうか。
難解な本であるから、余計ありがたがられているのではなかろうか。
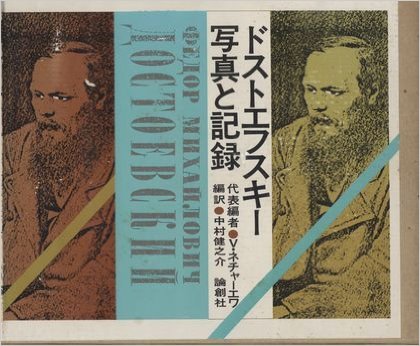
中村健之介訳、論創社、昭和61年、320頁、5,800円
原著は1972年発行。作家の生涯と作品を資料によって解説する。「読む資料」と「見る資料」に分かれる。
読む資料では作品や書簡等の抜き書きで全体像を捉えられ、また同時代の批評が載っている。
見る資料は多くの写真から成り、インターネットで簡単に見ることができるようになった現在でもここに収められている、凡ての写真を見られないだろう。
今の人の評価より、当時の評価や事実を知りたい自分にとって結構気に入っている本。
横長の大型のアルバムのような本だ。写真が多いからアルバムでも構わないが。
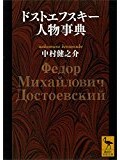
講談社学術文庫、2011年、574頁、1600円
題名のような人物事典でない。登場人物を手掛かりにしたドストエフスキーの作品論である。
1『貧しい人たち』から31『カラマーゾフの兄弟』に至る創作を取り上げ、論じている。
創作全体の内容や見方を元の小説を読まずに知りたい向きにも役立つであろうし、読んだ人も自分の理解との対比で読めば面白いだろう。
元々1990年、朝日新聞社から出版された。
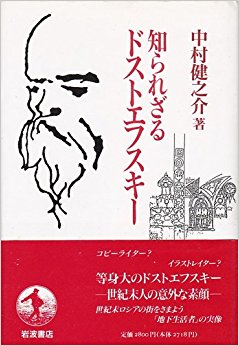
岩波書店、1993年、280頁、2,800円
ドストエフスキーには知られていないこんな一面があった、という類の本でない。
ドストエフスキーに親しんだ読者にとって関心があるであろう、作家や作品等についてまつわる情報を説明した本である。
目次は次のとおり。
「ドストエフスキー文学の主役たち」「ドストエフスキーの描いたスケッチ」「『罪と罰』のセンナヤ市場界隈」「軽妙なフェリエトン」「ドストエフスキーの父ミハイル」「友人ストラーホフの「観察」」「手紙に見るドストエフスキーの想像力」「ドストエフスキーとスウェーデンボルグ」「ドストエフスキーの文明観」
ドストエフスキー好きには知っておいてよい、または改めて整理しておいてよい事柄である。
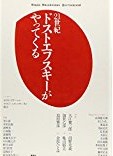
集英社、2007年、357頁、2,500円
全体は、「対談」「インタビュー」「評論」「私とドストエフスキー」に分かれ、多くの論者が参加している。
対談は三組ある。島田雅彦+金原ひとみ、大江健三郎+沼野允義、加賀乙彦+亀山郁夫である。そのうち大江と沼野の対談では、大江がドストエフスキーを形而上学的には読まない、と言っているところが面白かったし、沼野の発言は情報として役立つ。加賀と亀山の対談では加賀がキリスト教的な読み方の必要性を説いている。
インタビューは袋正、アクーニン、ソローキンの三人。現代ロシヤの作家二人に対するインタビューは、現在のロシヤのドストエフスキー理解の例がわかって面白い。ドストエフスキーは現代ロシヤでもブランド(ソローキン)だそうだ。(同書p.165)
評論は20以上、「私とドストエフスキー」も10以上の稿から成る。
前年からの亀山訳カラマーゾフによる、ドストエフスキーブームに乗った刊行だろうが、最近のドストエフスキー理解を知ることができる。

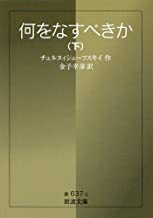
金子幸彦訳、岩波文庫、(上)、1978年、385頁、800円(2004年、7刷)、(下)、1980年、387頁、800円(2004年、5刷)
1863年、「現代人」(同時代人)誌に掲載された。チェルヌイシェフスキーはドストエフスキーの論敵で進歩派の作家である。ドストエフスキー好きなら『地下室の手記』(1864年)が本書に対する反論として書かれた、と知っているだろう。
しかしながら何も事前知識もなく本書を読み始めた現代の読者はどう思うであろうか。進歩的な女性を巡る三角関係の小説とまず感じるであろう。本書下巻のカバー裏には「社会主義的空想小説」とある。これは作中、女主人公が経営を試みる工場が共同主義であり社会主義の実践として描かれているところに顕著である。
発表当時、進歩派に支持、共感された小説であるが、ドストエフスキーはその思想に全く感心できなかった。
本書名を見て社会主義文献に詳しい者なら、レーニンの党組織論(1902)を思い浮かべたかもしれない。本書はレーニンの愛読書であり、同じ名を用いたのである。
読まれる時代によって読者の受け取り方が違うのは当然である。本書はそれが顕著な例である。

川端香男里訳、中公文庫、332頁、1984年、490円(1990年再版)
題名とおり19世紀のロシヤの作家の在り方や社会等を解説した著書で、原書の改訂版は1977年に出された。図版多数。1967年の初版は平凡社から訳が出ていた。目次は次のとおり。
第二版への序、序論、I 作家の立場、1 1825年から1904年までのロシア文学、2 作家の生活と使命、II ロシア帝国、3 地理、4 交通手段、5 民族、6 経済、7 皇帝たち、III 社会的背景、8「階級」、9 農民、10 領主と貴族、11 宗教、12 都市、IV 法と無秩序、13 官吏、14 罪と罰、15 軍隊、16 教育、17 雑誌と検閲、18 反体制、訳者あとがき、参考文献、索引
著者ヒングリーは1920年スコットランド生まれ、本文庫刊行当時はオックスフォード大学でロシヤ文学を講じていたという。
ドストエフスキー好きと限らず、ロシヤ文学に関心があれば座右に置きたい書である。

田中正人訳、世界の名著中公バックス第42巻、590頁、1980年、980円
ドストエフスキーは社会主義思想の時代に生きた。若い時にはペトラシェフスキー事件に関わり合い、その後作家に復帰してからは反社会主義の思想家となった。
そのドストエフスキーにとって、また生きた時代のロシヤにとって、代表的な社会主義思想家はフーリエ(1772~1837)であった。著作にも何度かフーリエの名が出てくる。
マルクス(1818~1883)はドストエフスキー(1821~1881)の同時代人である。『罪と罰』公表の翌年、1867年に『資本論』第一巻が刊行された。同じ時期の活躍で、まだマルクスは絶対的な権威となっていない。社会主義と言えばマルクス主義となったのは、ドストエフスキーより後代である。ただドストエフスキー存命中からマルクスは次第に影響力を増してきた。
ドストエフスキーはマルクスについて一箇所だけ言及している。
『政治論』(1873)で、ローマの教皇の世界制覇にはマルクスもバクーニンも敵わないだろうと言っている。(第4節、新潮社版全集第25巻、p.178)
ドストエフスキーにとってローマ・カトリックも社会主義も同じ穴の狢であった。その社会主義勢力の代表としてマルクスをバクーニンと並んで挙げている、この頃になるとそう評価していた。
現在、最も簡単に読めるフーリエの著作の一つはこの中公世界の名著で、オウエン、サン・シモンと共に収録されている。
フーリエはファランジュと呼ばれる協同社会を提唱した。人の間に働く、情念引力を満足させれば進んで労働に就くという。
ドストエフスキー自身がフーリエの著作を若い時でさえ読んだかどうか疑わしい。マルクスの著作を全く読んでいないマルクス主義者はいくらでもいた。
ドストエフスキーの理解に資するかどうかは別だが、当時の社会主義思想を形作っていた考えとして関心を持って読める。
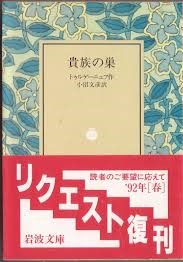
貴族の巣、小沼文彦訳、岩波文庫、312頁、1952年、570円(1992年第3刷)
けむり、神西清訳、河出版世界文学全集第9巻「プーシキン、ツルゲーネフ集」昭和37年、1,300円(昭和49年26刷)
ドストエフスキーとツルゲーネフの不仲は『悪霊』のところで書いたが、ドストエフスキーはツルゲーネフの芸術そのものは高く評価していた。
ここではドストエフスキー自身の言及のある、プーシキン講演で称賛したリーザが出てくる『貴族の巣』、またドストエフスキーを痛く憤慨させた西洋主義者ポトゥーギンが出てくる『けむり』を挙げる。

「サンクト・ペテルブルグ」小町文雄、中公新書、250頁、2006年、820円
ペテルブルグの特徴、歴史などが簡潔にまとめられている。
著者は外務省でソ連大使館勤務、後、学者となり大学教授等を勤めた。

St. Petersburg(Eyewitness Travel Guides),
by Catherine Phillips and others,
Dorling Kindersley Publishers Ltd
がある。英語が苦手であってもカラーの写真と地図を見ているだけでも楽しめる。