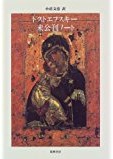創作以外の作品、創作ノート、その他の評論等、ドストエフスキーの部屋、副頁
創作以外では便宜的に以下の四つの分類に分ける。
本副頁では創作ノートとその他の評論等を載せる。『作家の日記』と書簡については別頁参照。
三種の全集には、基本的に後期の長篇小説を対象とした創作ノートが載せられている。しかしその掲載の仕方も、また内容、量に違いが見られる。
創作ノートはドストエフスキーが執筆に先立き、案等を綴ったメモ(と言っても長文が多い)であり、他人の目に触れることなど一切考慮していないため、残っているものを単に見ても前後関係も日付もわからず、その読解、整理は困難を極めた。
アンナ夫人が所蔵していたドストエフスキーの創作ノートは夫人の死後、1918年にモスクワの中央文書保管所に預けられた。3年後にそのノート類は開封されたが、整理、編纂のため更に十年以上経った1931年以降に、公表されるようになった。その後も創作ノートの整理は続けられ、現時点では過去の研究を踏まえた1972年以降の刊行である旧ソ連版ドストエフスキー全集(30巻)の創作ノートが標準のようである。
以下ではまず三種の全集の創作ノートの載せ方を述べ、次に小説毎に創作ノートの違いを述べる。
河出版米川訳全集
河出版全集では小説の巻に当該小説の創作ノートを載せる形になっている。
第6巻 罪と罰、創作ノート、昭和44年、738頁、980円
第8巻 白痴(下)、創作ノート、賭博者、昭和44年、477頁、980円
第10巻 悪霊(下)、創作ノート、永遠の夫、昭和45年、501頁、980円
第11巻 未成年、創作ノート、偉大なる罪人の生涯、昭和44年、650頁、980円
第13巻 カラマーゾフの兄弟(下)、創作ノート、昭和44年、534頁、980円
なお他社の全集の創作ノート編に含まれる「シベリヤ・ノート」は第20巻論文・記録下に収録。
新潮社版全集
2巻に分けて創作ノートを収録している。訳は各小説の訳者が担当。
第26巻 創作ノート(I)、1980年、509頁、1500円
『罪と罰』創作ノート、工藤精一郎訳、『白痴』創作ノート、木村浩訳、『悪霊』創作ノート、江川卓訳、「シベリア・ノート」、染谷茂訳
第27巻 創作ノート(II)、1980年、489頁、1500円
『未成年』創作ノート、工藤精一郎・安藤厚訳、『カラマーゾフの兄弟』創作ノート、原卓也訳、「大いなる罪人の生涯」、江川卓訳、
「実現されなかったプラン」、江川卓訳、「手帖より」、江川卓、工藤精一郎、原卓也訳
なおこの第27巻は新潮社版全集の最終回配本であったため、第24、25巻評論に載せるべきであった、評論の補遺が収録されている。これはその他の評論等で述べる。
筑摩版小沼訳全集
3巻を費やし以下の構成。
第18巻、創作ノート、I、『罪と罰』創作ノート、『悪霊』創作ノート、昭和58年、513頁、5900円
第19巻A、創作ノート、II、『未成年』創作ノート、1991年、522頁、7800円
第19巻B、創作ノート、III、『シベリヤ・ノート』、『白痴』創作ノート、『大いなる罪びとの生涯』創作ノート、『カラマーゾフ兄弟』創作ノート、1989年、466頁、7000円
19巻がA、Bと分かれているのは当初の予定よりページ数が多くなったため
『罪と罰』創作ノート
河出版米川訳全集第6巻
原典 グリヴェンゴ編『ドストエーフスキイの原資料より 罪と罰――未発表資料』1931年を基に米川が編集したもの、四六判二段組で173頁
新潮社版全集第26巻
原典 オブーリスカヤ、コーガン編『手稿』1970年、30巻全集も参照。四六判二段組で211頁
筑摩版小沼訳全集第18巻
原典 30巻全集第7巻、1973年、手稿1970年も参照。
『白痴』創作ノート
河出版米川訳全集第8巻
原典 サクーリン、ベーリチコフ編『ドストエーフスキイの原資料より 白痴 未発表資料』1931年の資料部分の完訳、四六判二段組で150頁
新潮社版全集第26巻
原典 ベリチコフ、サクーリン編『ドストエフスキー古文献より『白痴』未公刊資料』1931年のうち第5ノート、30巻全集も参照。四六判二段組で80頁
新潮社版全集版の『白痴』創作ノートが同じ原典の河出版全集に比べ頁数が少ないのは、破棄された以前の稿のノートを含まないためである。
筑摩版小沼訳全集第19B巻
原典 30巻全集第9巻、1974年、ベリチコフ、サクーリン編『F・M・ドストエフスキー古文献より『白痴』未公刊資料』も参照。
『悪霊』創作ノート
河出版米川訳全集第10巻
原典 コンシナ編『ドストエーフスキイの覚え書ノート』1935年の抄訳、原書の約十分の一、四六判二段組で105頁
新潮社版全集第26巻
原典 コンシナ編『ドストエフスキーの手帖』1935年、30巻全集(1975)を参照。四六判二段組で141頁
筑摩版小沼訳全集第18巻
原典 30巻全集第11、12巻、1974、1975年。コンシナ編『F・M・ドストエフスキーの手帖』1935年を参照。
『未成年』創作ノート
河出版米川訳全集第11巻
原典 ブロードスキイ、コマローヴィチ、ドリーニン訳編『知られざるドストエーフスキイ』(独書)1926年、四六判二段組で24頁。米川が本創作ノートを訳した当時(昭和27年)は原語の『未成年』創作ノートが全く利用できず、やむなく独訳の上記書を利用したとのこと。
新潮社版全集第27巻
原典 文学遺産シリーズ第77巻ジリベルシテイン、ローゼンブリュム監修、ドリーニン編『“未成年”の創作過程におけるドストエフスキー、創作ノート』1965年。30巻全集第16巻1976年を参照。四六判二段組で113頁。全体の約五分の一の訳出。
筑摩版小沼訳全集第19A巻
原典 30巻全集第16巻1976年。ジリベルシテイン、ローゼンブリュム監修『文学遺産』シリーズ第77巻1965年を参照。
『未成年』創作ノートは量が多く、小沼訳筑摩版全集ではこれだけで1巻を占めている。小沼訳筑摩版全集第9巻の『未成年』の本文が574頁あるのに対し、この創作ノートの本文は518頁である。
『カラマーゾフの兄弟』創作ノート
『カラマーゾフの兄弟』の創作ノートは以下の点で他小説と異なる。
形式的には他の小説の創作ノートが一応まとまったノート類に残されているのに対し、バラバラの大きさや種類の異なる紙片に記されている。
また、最終稿の創作ノートしか残ってなく、元々あったはずのそれ以前の初稿等の草稿、メモは紛失してしまっている。
河出版米川訳全集第13巻
原典 ドリーニン編『F・M・ドストエーフスキイ 素材と研究』1935年。四六判二段組で128頁。
新潮社版全集第27巻
原典 ドリーニン編『F・M・ドストエフスキー、資料と研究』1935年、30巻全集第15巻を参照。四六判二段組で126頁。全体の6割を訳出。
筑摩版小沼訳全集第19B巻
原典 30巻全集第15巻。ドリーニン編『F・M・ドストエフスキー、資料と研究』1935年を参照。
後期長篇小説群の創作ノートの各全集の違いについて
初めに述べたように、旧ソ連版30巻全集(1972年以降)が現在のところ最新の版である。筑摩版小沼訳全集はこれに基き各創作ノートを全訳している。断簡零墨に至るまで蒐集するのが全集という考えからは、筑摩版小沼訳全集が望ましい。他の全集は抄訳である。そのため小沼はあとがきで他の全集の創作ノートをケチョンケチョンに言っている。
他の全集の意義はどうか。
河出版米川訳全集は、過去のドストエフスキーの翻訳史、受容史の観点から古典というべき訳である。最も分量の多い『未成年』創作ノートを米川が訳した当時は原典が利用できず、独訳から苦労して訳した経緯など時代を感じさせる。
新潮社版全集は抄訳であるが、この当時、30巻全集は既に利用できた。ただ抄訳となっている。これは巻数ページの制約による。最初から創作ノートの巻数を決め、その中で調整した。善意に解釈すれば、創作ノートは専門家の研究用資料というべきものである。
我々のような素人が読む際、第一次接近として、さわり、重要と思われる部分を読むという手は悪くないかもしれない。創作ノートは読者を対象とした読み物ではないからである。もちろんこんなことが言えるのは、筑摩版小沼訳全集で全体を読めるからである。
なお河出版米川訳全集と新潮社版全集は、本の大きさも同じで8ポンイト2段組なので、ページ数の比較がしやすいと思い(河出版全集の方がややページ当たりの字数が多いように見える)、抄訳であるから各ページ数を書いておいた。
創作ノートを読んで作品の理解が深まるであろうか。完成する前の下書きのようなものであり、破棄されてしまった内容もある。
小説家の丹羽文雄は『小説作法』(昭和29年初刊)で、書くための覚書は捨ててしまっている、外に出す覚書は改まって書いたものである、と述べ、
「しかし生ま生ましい、ごちゃごちゃした覚書があれば、その作者の小説づくりの楽屋がさらけ出されることになる。」(講談社文芸文庫、2017、p.10)
と言っている。
ここで書いてあるように、ドストエフスキーの小説づくりの楽屋がわかるだろうか。
文学の研究と聞いても何をやっているのかよく知らないが、例えばドストエフスキーの創作ノートからみた何々の創作過程とかなら、専門家の研究のように聞こえる。
シベリヤ・ノート
ドストエフスキーがシベリヤ流刑時代、監獄や兵舎で聞き取った台詞を集めたもの。囚人らの口癖、ことわざ、民謡等を集めたものである。全部で486条まで番号が振ってあるが、欠番等あり若干少ない。シベリヤ・ノートは通称であり、ドストエフスキーがつけたものではない。後の『死の家の記録』を初め、諸作品に使われている表現集であり、これ自体当時の監獄の実態を伝える資料といえる。
一種の創作ノートに違いないが、他の創作ノートと違い、読んでいて面白い。
河出版米川訳全集第20巻(論文・記録下)、抄訳である、昭和46年
新潮社版全集第26巻、1980年、染谷茂訳(シベリア・ノート)
筑摩版小沼訳全集第19B巻、1989年
大いなる罪人の生涯
本編は『白痴』終了後、ドストエフスキーが生涯をかけた大作として構想した作品の創作ノートである。当初は『無神論』と題されていた。その構想は知人等にあてた書簡によってうかがえる。(1868/12/11マイコフ宛、1869/1/25イノーノワ宛、1870/3/24ストラーホフ宛、1870/3/25マイコフ宛等)
主人公は中年になってから信仰を失った人物である。意識していた『戦争と平和』なみの大作で、幾つかの篇に分かれ、修道院を舞台とする篇がある。
この創作ノートは1869年から1870年にかけて書かれた。周知のようにネチャーエフ事件が起り、ドストエフスキーは『悪霊』の執筆を始めた。その後『未成年』『カラマーゾフの兄弟』が書かれ、本『大いなる罪人の生涯』は執筆されずじまいに終わった。しかし本創作ノートを見れば、後期の長篇小説群に生かされていることがわかる。
なお本ノートの題は大きな罪を犯した者の伝記、くらいの意味らしい。人口に膾炙している『偉大なる罪人の生涯』では、罪人が偉大と誤解されやすい。
河出版米川訳全集第11巻、昭和44年(偉大なる罪人の生涯)
新潮社版全集第27巻、1980年、江川卓訳
筑摩版小沼訳全集第19B巻、1989年(『大いなる罪びとの生涯』創作ノート)
実現されなかったプラン
新潮社版全集第27巻では、実際には書かれなかった小説のプランを20篇ほど載せている。他の作品の創作ノートや『手帖より』に載ったもの以外で主要なプランが集められている。もっともここの案で実際に執筆された小説に生かされたものがある。
このうち『すばらしい構想、失念せぬこと』(1870年)は解題で江川卓が書いているようにドストエフスキーの自伝小説のようなものだった。
「小説家(作家)。老年になり、主として発作のために、さまざまな能力が鈍化し、つづいて貧困に陥る。(以下略)」(同巻、p.305)
この作は実現してくれれば良かったのにと思う。
ところで本篇の原典は凡例によると、コンシナ編『ドストエフスキーの手帖』、「文学遺産」シリーズ第83巻(『未完のドストエフスキー』)、グロスマン編新潮社版全集別巻、文集『埋蔵物』などを用い、30巻全集を参照とある。よく分からないのは、この『実現されなかったプラン』は新潮社版全集にしか収録されていない。
古い時期の翻訳である河出版米川訳全集に入っていなくても不思議ではないが、なぜ筑摩版小沼訳全集には入っていないのか。この新潮社版全集第27巻は1980年の刊行である。筑摩版小沼訳全集の最終回配本が1991年で1997年に補巻として『ドストエフスキー未公刊ノート』を出している。十分どこかで収録できたはずである。
当方が見落とし等しているかもしれない。わかり次第追加する。
新潮社版全集第27巻、1980年、江川卓訳。
手帖より
創作ノートの初めに書いたように、ドストエフスキーが自らのためにつけていたノート(手帖、雑記帳)は、整理されておらず、複数のノートを同時平行的に利用しており、前後関係さえ不明である。その中で各小説の創作に関わる部分が、上に述べた創作ノートである。
それ以外にもドストエフスキーは様々なメモを書きつけていた。
それらの集大成が、1971年に出された「文学遺産」シリーズ第83巻「未完のドストエフスキー」である。もっともそれ以前から一部は公表されており、早い時期では作家の死後、ドストエフスキー全集第1巻(1883)に『ドストエフスキーの手帖より』と題して晩年の断想的な文章が公表されていた。
内容は覚書であり、「作家の日記」的な意見、ただ公表用ではないので本音が書いてある。また他の作家、作品への感想、作品の改作案(『分身』)など様々である。
三種の全集のうち、河出版米川訳全集第20巻論文・記録下では『手帖より』と題し、上記の1883年全集からの翻訳である。そのため時期も偏っており、量も少ない。
他の二社は「未完のドストエフスキー」(1971)を踏まえている。
新潮社版全集では第27巻に『手帖より』として、全体の約三分の一を訳している。しかしながら全体の約七分の一は計算書類(家計簿の類)で、これを除けば実質的には約二分の一にあたると解題にある。
さて筑摩書房の小沼文彦訳では、全集には入っておらず、後に補巻として出された『ドストエフスキー 未公刊ノート』1997年、筑摩書房、176頁、6,200円がそれにあたる。
なぜ筑摩版全集に入っていないのか。筑摩版全集は3種の全集のうち刊行開始が最も早く(昭和37年)、その時は上記『未完のドストエフスキー』はまだ発刊されていない。そのため補巻として発売したのだろう。
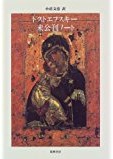
本『ドストエフスキー 未公刊ノート』の目次は次のとおり。
1.メモ・ノート(1860-62年)、2.同(1863-64年)、(妻マーシャの死)、 3.同(1864-65年)、4.同(1864-66年)、5.同(1864-65年)、6.同(1872-75年)、7.同(1874-75年)、8.同(1875-76年)、9.同(1876-77年)、10.同(1880-81年)
エムスでの療養日記(1874年)
メモ・ノート補遺
癲癇発作の記録(1861−80年)
この『ドストエフスキー 未公刊ノート』の凡例に「わが国ではこれまで完全なものが刊行されたことのない、ドストエフスキーの『雑記帳』、つまり「メモ・ノート」の類であり、筑摩書房刊「ドストエフスキー全集」の補巻となるべきものである。」とある。原典は1971年「文学遺産」シリーズ第83巻『未完のドストエフスキー』(ジリベルシュテイン、ローゼンブリュム編)で、30巻全集を参照とある。
新潮社版全集第27巻『手帖より』と筑摩書房『ドストエフスキー 未公刊ノート』の比較
新潮社版全集第27巻の『手帖より』と比較する。
まず『ドストエフスキー 未公刊ノート』の別掲を比較する。「エムスでの療養日記(1874年)」。これは1874年6月25日から7月25日までの、エムスでの療養の記録である。普通の日記である。
これは新潮社版全集第27巻『手帖より』のp.351~353に訳出されている。
「メモ・ノート補遺」とは、1874年9月4日のドストエフスキーの息子が話してくれたおとぎ話から始まる箇所である。
ここの部分は新潮社版全集第27巻『手帖より』のp.354~356に訳出されている。
なぜここの部分を小沼訳では補遺としているか不明である。『ドストエフスキー 未公刊ノート』には冒頭の凡例のみで、あとがきや解説がない。原典で補遺となっているもしれない。もしそうなら新潮社版全集では本文に入れたということか。
「癲癇発作の記録(1861−80年)」は新潮社版全集第27巻『手帖より』の、p.321、p.337~338(1864年の8月は若干の違いがある)、p.349~351(ここの部分で書き方の相違があるが、情報量は同じ。)また両者の違いの話でなく、1874年4月以降の記録では単に日付にとどまらず、どのように症状で苦しんだかの記述がある。ドストエフスキーの癲癇の症状の記録として重要(小沼訳p.173~、新潮社版全集第27巻p.349~351、p.428~430、p.438~439)。なお新潮社版全集には1875年9月22日分がないようである。小沼訳のp.175にある。新潮社版全集第27巻のp.429の9月29日の前にあるはず。
自分が照合した限りでは『ドストエフスキー未公刊ノート』の別掲「エムスでの療養日記(1874年)」「メモ・ノート補遺」「癲癇発作の記録(1861−80年)」に関しては1875年9月22日の癲癇発作の記録(3行)を除き、新潮社版全集第27巻に凡て含まれている。
新潮社版全集第27巻の解題で同巻『手帖より』は全体の実質的に二分の一と言っているので、『ドストエフスキー 未公刊ノート』で別掲以外のメモ・ノートと題される1.から10.のうちには、新潮社版全集第27巻に含まれていないメモがそれなりにあるはずである。
内容
1864年の最初の妻マーシャの死に際して、ドストエフスキーが死生観、宗教観を語ったメモは有名。新潮社版全集第27巻、p.322以下、『未公刊ノート』p.20以下の他、中村健之介『ドストエフスキー、生と死の感覚』岩波書店、1984年、『やさしい女、白夜』安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2015年にも訳されている。
『作家の日記』の創作メモといったものも多く、自らのメモであるため率直な意見が多く、また簡潔である。
トルストイやツルゲーネフなど他の作家の評なども面白い。キリスト教と社会主義についての論文案の他、アジアについては「アジアなんてくそくらえだ」に始まり、ユダヤ人、英米人に委託すればよい、最初の誤りがあまりに長く続いている、などと書いている。(新潮社版全集第27巻、p.437~438、『未公刊ノート』p.161~162)
ともかく公表物でないので好き勝手に書いている感じ。
『分身』(『二重人格』)の改作案メモもある。メモで終わったが、不評だった同作を修正するつもりだった。
エムスで時間があれば読みたいと言っている本のリストも興味がある。(新潮社版全集第27巻、p.355~356、『未公刊ノート』p.170~171)
『ボヴァリー夫人』が一番有名か。ミュッセの『世紀児の告白』は岩波文庫にある。他に
ジョルジュ・サンド『若き娘の告白』『セザリーヌ・ディートリッヒ。戦時下における一旅行者の日記』、デュマ『クレマンソー事件』、デュマ=フィス『戯曲 男・女』などは翻訳されているのか。他に名前が挙がっている作家、エルクマン=シャトリヤン、ベロ、フウイエなど知らない。プルードンの『12月2日のクーデターによって証明された社会革命』も知らない。「ゾラの小説について」ともある。(以上の訳名は新潮社版全集から)
以下のドストエフスキーの文学評価も面白い。
「今世紀の美しいもの。ピクウィック、『ノートル・ダム』、『ミゼラブル』、ジョルジュ・サンドの初期の作品、バイロン卿(びっこ)、レールモントフ、ツルゲーネフ、『戦争と平和』、ハイネ、プーシキン。
ウォルター・スコット、彼は正統王朝派ではない。過去への憎悪のうちの、賢明な、気高い心からの和解だ。『ノートル・ダム』はちがう、憎悪等々(音楽)。」(以下略)
(新潮社版全集第27巻、p.375、『未公刊ノート』p.86)
ドストエフスキーは、ノートの他の部分でもツルゲーネフをやっつけているが、優れた芸術を挙げる際は必ず入れている。
計算書類
ここで気になる点を補足する。新潮社版全集第27巻の解題によれば、全体の七分の一に達する計算書類(家計簿の類)があるが、「計算書の類は原則として割愛する。」(同巻p.488)としている。例示的に訳されているものは次のようである。(同巻、p.315)
| 支出案 |
| パリビン(家主の商人)へ<1861年>10月 |
| 一日まで総計 | 105 |
| 新居への引越し、整備 | 170 |
| パーシャ(継子イサーエフ) | 60 |
| 外套 | 40 |
| マリヤ・ドリートエヴナ、借金 | 21 |
| 彼女の服代 | 100 |
| 仕立屋 | 60 |
| シャツ | 10 |
| 小物 | 20 |
| 11月1日までの生活費 | 300−[100] |
| 現金 650ルーブリ |
(以下略)
新潮社版全集第27巻『手帖より』ではこの他、p.331、p.333、p.353~354に数字の記録の訳がある。
それに対して『ドストエフスキー 未公刊ノート』では、凡例にこの計算書の言及はなく、当然一切訳されていない。
このような数字の羅列は多くの読者にとって興味がないだろうし、ドストエフスキー理解の助けにもなりそうにないという判断であろうか。
ここで個人的な意見を言わせてもらう。自分としてはこの計算書類には関心があり凡て訳して欲しかった、というところが本心である。書簡を読むのはドストエフスキーの文学理解のためでなく、ドストエフスキーに関心があるから、が自分の理由である。それと同様にこのような支出記録に興味があるのである。文学の専門家たちは数字に対し関心が低いようで残念。
河出版米川訳全集第20巻、(論文・記録下)、抄訳である、昭和46年
新潮社版全集第27巻、1980年、抄訳である、江川卓、工藤精一郎、原卓也訳
『ドストエフスキー 未公刊ノート』1997年、小沼文彦訳、筑摩書房
『作家の日記』を除く評論は、現在出ている全集で違いがある。以下の書名、順序は新潮社版全集を基にした。
その他の評論等については以下に留意する必要がある。
多くはドストエフスキーが編集していた雑誌等に無署名で発表された。そのため当時の知人や後代の研究家がドストエフスキーの作とみなした文章が全集に収録されている。
またドストエフスキーの単著でなく、他の著者との共同執筆、及び編集者としての立場で書いた文章がある。これらは河出版全集では第二部(第一部が単著)として第20巻に、筑摩版全集では補遺Iとして第20B巻に収められている。新潮社版全集は最初に単著を収め、続いて共著、編集部としての文章が第25巻にある。ただし全集によって著作が単著、共著等にいずれに含まれるかが違う。
さらに新潮社版全集は第25巻解題p.401に、翻訳時に30巻全集が間に合わず、戦前の13巻全集によっている(河出版全集も同じ)とあるが、一部30巻全集初出の文章もある。筑摩版全集は30巻全集を参照しているので、この30巻全集で初めて収録された文章(第20B巻の補遺II)が含まれている。もっとも筑摩版全集第20B巻あとがきp.403に「翻訳のテキストとしては最も信用のおける十三巻全集の第十三巻を用い、三十巻全集の第十八、十九、二十、二十一巻を参照して補足した。」とある。
茶化し屋
1845年「祖国雑記」
ネクラーソフが企画した文集「茶化し屋」の広告である。この文集そのものは実現されなかった。茶化し屋(ズボスカール)は、ロシヤ語で歯をむき出して笑う人と言う。軽妙さとユーモアを併せ持った本広告文は話題になったと兄ミハイルに書いている。(1845/11/16)
河出版米川訳全集第19巻(ズボスカール)、昭和46年
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻(ズボスカール)、昭和56年
ペテルブルグ年代記
1847年「サンクト・ペテルブルグ報知」
5篇から成るが、最初の一篇(1847/4/13)はドストエフスキー著ではないと言われている。
年代記といってもペテルブルグの歴史が書いてあるわけではない。
本編はペテルブルグを対象にしたフェリエトンである。フェリエトンとは何か。雑誌や新聞に欄を設け、そこである話題について論じ著者は批評する。対象は文学でも演劇でも政治でも風俗でもなんでもいい。雑録ないしコラムである。19世紀初頭のフランスで始まり、ロシヤに輸入された。ドストエフスキーの創作以外の公表物はフェリエトンといっていいものが多い。
本編ではペテルブルグの住民、劇場、建築、夏に別荘へ住民が行った後の街などが語られる。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年
なお、この巻所載の『ペテルブルグ年代記』は1847年6月1日分が抜けており、これは第20巻の補遺で息子が訳している。
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
小沢訳全集20A巻では、ドストエフスキー作でない疑いが強い最初の一篇をはずし、ただドストエフスキーの関与があるという理由でそれを20B巻の補遺に追加している。
裁判記録
新潮社版全集第24巻に収録されている、ドストエフスキーの供述はベリチコフ編「ペトラシェフスキー事件におけるドストエフスキー」(1936)による。
ドストエフスキーの逮捕は1849年4月23日で、5月6日に供述があり、それに基き訊問が6月に行なわれたようである。判決は12月19日である。
新潮社版全集の『裁判記録』はドストエフスキーの証言集である。逮捕されたドストエフスキーは神妙に尋問に答えている。
個人的に特に興味を持ったところは、次のとおり。
ドストエフスキー自身が自分の身分や家族、宗教、経歴、財産などを述べているところ(新潮社版全集第24巻、p.70)。
どうして自由主義的、社会的傾向が現れてきたか、を訊かれ、自分は改革を望んだがそれは専制に期待していた、社会主義者だったことは一度もない、西欧の変動に興味を持っていた、社会主義の理論体系は誤りであり、フランスにおいてさえそれを適用したら避けがたい破滅を招くであろう(同書、p.95~96)。
裁判記録に関しては原卓也・小泉猛編訳『ドストエフスキーとペトラシェフスキー事件』集英社、昭和46年に、本全集第24巻と同じ原卓也訳の内容がある。
裁判関連全体に関してはN・F・ベリチコフ編中村健之介編訳『ドストエフスキー裁判』(北大出版会、1993)が別途刊行されており、原本はこの新潮社版全集第24巻と同じである。
新潮社版全集第24巻では「ドストエフスキーの供述書」「ドストエフスキーに対する人定訊問」「ドストエフスキーの個々の供述」ほか4編が含まれている。更に第25巻補遺に24巻に含まれていなかった3編が追加されている。(第25巻、p.394)
第25巻補遺を含め、新潮社版全集の記録は凡て『ドストエフスキー裁判』に含まれている。『ドストエフスキー裁判』では他にドストエフスキー逮捕命令、ドストエフスキーの退役証明書とゴリーツィン公爵の送り状、ドストエフスキーに関する記録抜粋、判決、皇帝の裁可などドストエフスキー自身の供述以外を含めた全23記録(章)から成る。
なおこのうち第2記録『逮捕の朝』は後年、ドストエフスキーが書いた、逮捕の状況の貴重な記録である。河出版米川訳全集第20巻、昭和46年、p.301~303に「L・ミリュコーヴァのアルバムに」として載っている。新潮社版全集については第22巻、1980年、書簡のうちp.425に1860年5月24日「ミュリコワのアルバムへ」にある。筑摩版全集についてはありかがわかり次第追加する。
新潮社版全集第24巻、1979年、原卓也訳
ロシヤ文学論
1861年「時代」
ヨーロッパはロシヤを理解していないという論から始まり、それではロシヤとは如何なる国か。ロシヤ民族は全人類の歴史の上で特異な現象である、といういつものドストエフスキーの主張である。ロシヤ人論が続いた後、プーシキンの全世界性という後年と同様の論になる。
第2章はドストエフスキーの芸術論が聞ける。
芸術に関する二つの見解。一つは芸術のための芸術派であり、もう一つは功利派、すなわち人間の利益に資すべきという考えである。それ自体で意味があるとする派と有用性で判断する派である。ドストエフスキーは前者である。功利派の**ボフ氏(評論家ドブロリューボフを指すという)への批判により成る章である。
そのドブロリューボフの論文が引用される。そのうちドブロリューボフがロシヤの精神、庶民の性格が表れているとして称賛する、作家ヴォフチョークの短篇『マーシャ』の引用が結構長い。同名の百姓娘に、自立性への愛と奴隷状態への嫌悪が芽生えていく様が描かれている。ドストエフスキーはこの作品を糞みそに貶す。一体この娘はどの人間だ、スウェーデンかインドかスコットランドかなどと問う。ドストエフスキーはロシヤの庶民を評価していたのではないか。しかしこんな進歩的というか自由と独立を要求する者ではなかったのであろう。もちろん内容のイデオロギー性の話でなく、芸術をどう考えるかの問題である。
ドストエフスキーは芸術をどう考えていたか。
芸術はそれ自体で有機的生命を持つ。芸術は人間にとって不可欠であり、美と美の創造への要求がなければ人間は生きることを欲しなかったかもしれない。人間は美ということだけで、その有用性でなく、畏敬する。以下、ドストエフスキーの芸術論が続く。
(河出版米川訳全集第19巻、p.72~、新潮社版全集第24巻、p.178~、小沼訳筑摩版全集第20A巻、p.118~)
続く第3章と第4章は「書物と読み書きの能力」と題される。
国民のための読書の必要性が議論された。国民向けの書物の欲求も出された。諸雑誌はロシヤの国民性について論じた。その中でプーシキンが国民性を持たないとする主張があり、ドストエフスキーは延々とプーシキン論を展開する。
国民が読むべき書物の案が出ていて、批判も出ている。
ドストエフスキーは読み書きを教えるべきと主張する。(19世紀前半のロシヤの識字率は5、6%、19世紀末のロシヤの識字率は約2割程度、貝澤哉『「厚い雑誌」の興亡』「21世紀ドストエフスキーがやってくる」集英社所収、同書、p.266、望月哲男訳『死の家の記録』光文社古典新訳文庫、p.29の注12)また民衆に教えてやる、といった押しつけがましい、恩着せがましい態度は反発を招くだけである。
推薦書の基準は、読書欲をおこさせるため、楽しい面白いものを選ぶべきである。
最後の第5章では西欧派とスラヴ派を対比。西欧派はリアリストであった。それに対しスラヴ派は朦朧たる不定の理想に留まっていた。ドストエフスキーはスラヴ派でも西欧派でもない土壌主義派(この言葉はここには出てこない、もちろんスラヴ派に近い)であった。
『ロシヤ文学論』はこれまで5章とされていた。最近「大学問題」を論じる『ロシヤ文学論』の章(1861年「時代」誌に公表)が研究によりドストエフスキーの執筆と見なされ、新潮社版全集の最終回配本第27巻創作ノート(II)、及び筑摩版小沼訳全集第20Bの補遺に入れられた。
大学は教育か研究かの古典的問題を論じている。ただ結構冷静に論じており、あまりドストエフスキーらしくない。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(ロシヤ文学について)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳(ロシア文学論)
新潮社版全集第27巻、1980年、染谷茂訳(補遺(ロシア文学論))
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(ロシヤ文学についての一連の評論)
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年、補遺I
ペテルブルグの夢――詩と散文にみる
1861年「時代」
冒頭、自らを雑文記者、雑記記者、コラムニストと名乗る。(夫々、新潮版、河出版、筑摩版の訳)『ペテルブルグ年代記』で述べたフェリエトンを書く記者という意味である。
語り手はフェリエトン記者の仕事を語り、過去の回想で幻想的なペテルブルクを述べる。夢想に耽る。隣に住んでいた少女、この回想は『貧しき人々』を思い出させる。また外国の英雄になったり、現実では街角で物乞いの少年に会ったりする。金持ちになっても乞食のようなふりをしていたい、など『プロハルチン氏』(1846)か『未成年』のアルカージイのような空想を述べる。流刑前の若き夢想家時代のような文である。
ドストエフスキーの評論は正直いって、読み進めるのがしんどい物が多い。その中で本編は読みやすく興味を持てる。一読を勧めたい。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(ペテルブルグの夢――詩と散文――)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(詩と散文からなるペテルブルクの夢)
誠心誠意の見本
1861年「時代」
ある上流婦人がプーシキンの詩を朗読した。それを嘲笑する批評が出て、更にその論をまた批判する文が出た。ドストエフスキーは自らの意見を言い、婦人を擁護している。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
「呼子」と≪ロシア報知≫
1861年「時代」
「ロシヤ報知」誌は、「現代人」誌の評論欄「呼子」を攻撃している。下らぬ文学上の議論をしていると。「呼子」欄の過大評価になっているように見える。ドストエフスキーにとって我慢がならなかったのは、「ロシヤ報知」がロシヤの後進性を指摘し、ロシヤの国民性とは何か、ロシヤ文学、ロシヤ美術や思想は何かと問う。ドストエフスキーは敢然と反論する。プーシキンがいるのではないか。後年のプーシキン賛と同じようなことを言っている。
脱線だが、呼子という言葉は懐かしい。合図のための笛。石川啄木の詩集『呼子と口笛』(明治44年作)を思い出す。「はてしなき議論の後」などが入っている。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(『口笛』と『ロシヤ報知』)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(「呼子」と「ロシヤ報知」)
L・K氏と「≪時代≫編集部宛てワシリエフスキー島からの手紙」に対する注
1861年「時代」
「ロシヤ報知」誌の文芸評論欄の質が低下している。冷静な状態に見えないと批判した短文。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(『ヴレーミャ』編集部にあてたヴァシーリエフスキイ島住人の手紙に対する注)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(L・Kの「『時代』編集部宛て、ヴァシーリイェフスキー島からの手紙」に対する注)
≪ロシア報知≫への答え
1861年「時代」
「時代」の以前の号に載った「「呼子」と≪ロシヤ報知≫」により、「ロシヤ報知」は批判されたことに怒っている。「時代」誌を女性解放論者と呼んでいる。(当時のロシヤで女性解放論者とは侮蔑の言葉であった)
またプーシキンの詩『エジプトの夜』についても論じている。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(『ロシヤ報知』への答え)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(「ロシヤ報知」への回答)
文学的ヒステリー
1861年「時代」
これもまた「ロシヤ報知」への批判であり、同誌の「時代」誌へのいら立ちは、ますます女性的なヒステリーのようなものになっていると述べる。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
≪ロシア報知≫の哀歌的記事について
1861年「時代」
これも同様に「ロシヤ報知」の記事の内容、論調への批判。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(『ロシヤ報知』の哀歌的感想について)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(「ロシヤ報知」の哀歌的記事について)
理論家の二つの陣営
1862年「時代」
二つの陣営とは理論家(西欧派)とスラヴ派である。ピョートル大帝の改革への評価がある。上層階級と国民の間の分裂というドストエフスキー的な話題。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
スラヴ派、モンテネグロ人および西欧派。ごく最近の論戦
1862年「時代」
モンテネグロ(セルビアの南の国)がトルコと戦っている。西欧派陣営の「現代の言葉」誌がモンテネグロに支援を行なった。スラヴ派の「日々」誌はいたく驚いた。「現代の言葉」誌の支援はスラヴ諸国のためでなく、独立と自由を求める戦い、という理由による。「日々」「現代の言葉」両誌とも自己主張する。両誌の論戦を批判する。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(スラヴ派、モンテネグロ、西欧派。ごく最近の論戦)
新潮社版全集第24巻、1979年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(スラヴ主義者、モンテネグロ人と西欧派。ごく最近の罵り合い)
デリケートな問題
1862年「時代」
誰が悪いのかという問いから始まり、西欧派の雑誌「現代の言葉」と、保守派の「ロシヤ報知」との論戦を扱っている。「ロシヤ報知」のカトコフがイギリス派であったため、議会の演説とヤジを再現したような書き方にしていると解説で知った次第。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(尻くすぐったい問題)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
さまざまなパン的・非パン的問題に関する必要な文学的釈明
1863年「時代」
「時代」誌に対する他誌の攻撃への反論。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(さまざまなパンにつながる問題とパンにつながらない問題に関する、必要不可欠な文学的釈明)
新しい文学機関紙と新しい理論について
1863年「時代」
当時のジャーナリズムへの批判、後半は村落に学校をつくらせようとするお上、また共に不正をする地主と農民、どちらの罪が重いかを論じる。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(新しい文学機関と新しい理論について)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(新しい文学機関紙と新しい理論に関する誌上短評)
誌上短評
1863年「時代」
1.「呼び子吹き」への回答と、2.若いペン、に分かれる。
「時代」誌への批判への反論、また自分の名を勝手に使っている別人に対して怒る文をからかう。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
再び「若いペン」
1863年「時代」
上記『誌上短評』で「現代人」誌の文を揶揄したので、「現代人」誌から反論が来た。その反論をからかっている。誰が書いたか分かっているぞと言う。後の『シチェドリン氏、・・・』で明らかにしている。
当時はマス・メディアと言えば印刷物しか無かった時代だから、今ならインターネット上の媒体でやればいいような論争を雑誌でしている。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(再び『若いペン』)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(ふたたび「若いペン」)
シチェドリン氏、別名ニヒリストの分裂
1864年「世紀」
“ニヒリスト”の雑誌同士「現代人」誌、「ロシアの言葉」誌間で争いがあった。ニヒリストとは新思想、進歩派を指す否定的な呼称だったらしい。そのうち「現代人」誌の主力メンバー、シチェドリン(サルトィコフ=シチェドリン)を風刺する。「現代人」誌はあのチェルヌイシェフスキーの『何をなすべきか』が掲載された進歩派の雑誌である。
ドストエフスキーはシチェドリンをシチェドロダーロフという名に替え、同名の小説の抜粋なるものを書いている。作家が雑誌との契約を破り自分の考えを載せたため、編集部と対立、内紛するという内容である。シチェドリン、「現代人」誌をからかった文である。
シチェドリンはドストエフスキーの論敵である。有名な小説家で『ゴロヴリヨフ家の人々』が岩波文庫から、また選集全8巻が未来社から出ている。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(シチェドリン氏、一名ニヒリストの分裂)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(シチェドリーン氏あるいはニヒリストの分裂)
兄ミハイル・ドストエフスキーについて数言
1864年「世紀」
7月10日に死亡した、兄であり雑誌の編集者であったミハイルへの追悼文。例によってドストエフスキーはミハイルをこの上なく立派な人格であったと称賛する。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(ミハイル・ドストエーフスキイについて数言)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(ミハイル・ミハイロヴィッチ・ドストエフスキーについて数言)
必要不可欠な声明
1864年「世紀」
『シチェドリン氏、別名ニヒリストの分裂』に対して「現代人」誌から攻撃があったのでその反論。ドストエフスキーだけでなく、ドストエフスキーの病気を知っているから、その医者まで「現代人」誌は馬鹿にする。納得できないと述べる。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(必要かくべからざる声明)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
けりをつけるために――「現代人」との最後の話し合い
1864年「世紀」
前論文『必要不可欠な声明』3ページに対して「現代人」誌は48ページもの反論を載せ驚いている。もうこれ以上「現代人」誌との論争をするつもりはないと述べる。
『誌上短評』の後半から、『再び「若いペン」』、『シチェドリン氏、別名ニヒリストの分裂』、『必要不可欠な声明』と続いてきた「現代人」誌との論争はこれで終わり。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(片をつけるために)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
ストラーホフ『アポロン・グリゴーリエフの思い出』によせて
1864年「世紀」
ストラーホフの文でグリゴーリエフの書簡が引用されている。ドストエフスキーは2点異議を唱えている。一つは故兄ミハイルがドストエフスキーを酷使し、その文才を大切にしていない、と書簡にあるので兄ほど自分の才能を評価してくれる者はなかったと誤りを正す。『虐げられた人々』の書き方は自分のせいである、と言う。他に『貧しき人々』」や『死の家の記録』の名も挙がっており、ドストエフスキーが外向きの文とは言え、自分の作品を述べている貴重な記録。
もう一つは「時代」誌の同人で後に同誌から去ったグリゴーリエフは、その素質が雑誌編集に向いていなかったと述べる。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(アポロン・グリゴリエフについて)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(注釈≪N・ストラーホフの『アポロン・アレクサンドロヴィッチ・グリゴーリイェフの思い出』に寄せて≫)
実生活と文学における地口
1864年「世紀」
新聞「声」及び雑誌「祖国雑記」の編集者の文を揶揄する。月刊雑誌は力を失い、新聞は得たという。とんでもない。多くの雑誌が部数を伸ばしている。「祖国雑記」は月1回でなく2回発行するという。それが何になるのか。
声が声明とか意見など様々な意味になる、また他の語にしても同様で、言葉の語呂合わせで遊んでいるような文章である。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(実生活と文学における語呂合わせ)
政治論 外国の諸事件
1873~1874年「市民」
ドストエフスキーは「市民」誌の1873年から1874年まで編集を担当し、同誌に「作家の日記」という欄を受け持ち、そこには文学、芸術系の文を載せた。それらは現在『作家の日記』にまとめられている。
ただそれ以外にもドストエフスキーは同誌に記事を載せていた。その中でも外国政治の論文をまとめたのが、この『政治論』である。米川正夫の命名で、原題は「外国の諸事件」である。新潮社版全集の染谷茂訳では米川による訳名の後、原題をつけている。小沼訳筑摩版全集では原題の直訳である『外国の諸事件』としている。
内容は当時のヨーロッパを対象とした国際政治評論である。ヨーロッパの大国であり要と見られていたフランスを中心にドイツ、オーストリア、イタリア、スペイン等の情勢を論じる。フランスでは普仏戦争の敗北後、共和派のティエールが国をまとめていたが、ドイツ軍の占領撤退となり、勢力のあった王党派との調整が必要になった。
王党派の中でも正統派(ブルボン派)とオルレアン派が対立していた。ブルボン派はシャンボール伯(アンリ五世と呼ばれた)、オルレアン派はパリ伯が代表であった。歴史の教えるとおりシャンボール伯は国旗を三色旗でなく、ブルボン朝の白旗にしようとこだわり、表舞台から去っていった。この評論の時点ではそこまで行ってなく、シャンボール伯が政権を取り王政復古となる可能性などをドストエフスキーは論じている。
フランスがカトリック、ドイツがプロテスタントの国家で、国家間の不和、争いを宗教的な面から論じているのは後の『作家の日記』だけでなく、この『政治論』にもある。教皇がプロテスタントも含めた全キリスト教徒は教皇に属すると言うので、社会主義と変わらない世界支配の目論みであるかのように論じる。
(以下は内容でなく、各全集の違いについてである)
細かい話だが、『政治論』には外国からの電報(今風に言えばニュース速報)が載っている章がある。その載せられている電報(の数)が三種の全集で違うのである。
新潮社版全集は電報の数が少なく、河出版全集が一番多い。筑摩版全集はその中間である。1873年9月24日号と1873年10月1日号である。
1873年9月24日の号で、新潮社版全集第25巻p.161にヴェルサイユ発、パリ発の2通だけで、その後に原注として「このあとさらに十一通の電報が続く。編集部注」とある。
筑摩版全集第20B巻ではp.179からp.181まで使い、残りの電報も載っている。p.183の注(4)に「以下十一通の電報はソヴェート版十三巻全集では省略されているので、三十巻全集によった」とある。
河出版全集第19巻ではp.191からp.192までに、筑摩版全集と同じく全部の電報が訳され、注に「以下の十一通の電報はソ連国立出版所版全集では省略されている-訳者」とある。
1873年10月1日の号は次の様である。新潮社版全集では電報は一切載っていない。第25巻p.167にある「・・・たくさんの新しいpronunciamento(抗命宣言)が布告されるだろう・・・」という本文の後になるはず。
筑摩版全集も同様に何もない。第20B巻p.187の注(7)に、「市民」誌には17通の電報が付録としてあり、内訳はパリ発が10通、ローマ発が2通などとあって「当然のことながらこれは文中にはなく付録であって、しかもドストエフスキーの作ではないので、ソヴェート版十三巻全集でも最近の三十巻全集でも省略されている。」とある。
河出版全集のみ電報が収録されている。全集第19巻p.198の本文の後に16通の電報の掲載がある。p.200の注に「以下の電報はソ連国立出版所版全集ではでは省略-訳者」とある。
これらの違いは以下の様な理由であろう。新潮社版全集では第25巻の解題p.401に、評論の巻は30巻全集の刊行が遅れているので、13巻全集(1926~1930)によったとある。その13巻全集には付録の電報がほとんど載っていないので、新潮社版全集では少ない。9月24日号は小沼訳全集の注にあるように、13巻全集では最初の2通しか載っていないので、残りは30巻全集によった。10月1日分は雑誌には掲載されたが、13巻全集でも30巻全集にも載っていないので、省略したとある。河出版全集はその付録の電報も訳した。
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(政治論)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(外国の諸事件)
宗教教育同好者協会の三月二十八日の会議
1873年「市民」
信仰統一問題(教会と分離した信徒との統合)について、異なる意見を持つ論者の一人が討論会に欠席した。欠席した論者の主張では、相手に勝てないだろうと述べている。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(三月二十八日宗教教育同好者協会の会合)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
I・F・ニーリスキー氏への回答 -編集部より
1873年「市民」
表題にある名は前回の記事にある会議を欠席した宗教大学教授で、その教授から前回記事の欠席理由が誤りであるという釈明文が来た。まずその教授の文章を載せ、それに対し反論している。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(編集部から(I・F・ニーリスキー氏への回答))
ニール神父の事件
1873年「市民」
修道院のニール神父の庵室で債券等の盗難事件が発生した。容疑者(被告)、被害者ともに女であった。二人ともニール神父と情交関係にあった。裁判では被告は無罪となった。この事件について歴史の中で考え、修道院に影響を及ぼすものでないとしている。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
編集者の感想二つ
1873年「市民」
一つは女子高等教育の件。モスクワに女子高等教育の学院が設立された。以前の号でそれを喜ぶと共に、高等教育を受ける女子は女性問題の解決の活動家という自信を持つ、と書いた。これに女子生徒から学んでいるだけだと反論が来た。その反論のとおりであれば結構だと述べる。
もう一つは雑誌間の批評のやり取りについてである。最近では全くどうしようもない、相手にできない批評が増えていると言う。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(編集者の覚え書き二つ)
流れゆく生活の中から
1873年「市民」
雑誌に載った作品を同じ雑誌で褒めるなどけしからん、と最近はされているらしい。昔ベリンスキーは「祖国雑記」に載った作品を同じ雑誌で絶賛の批評を書いて、誰も何も思わなかったのに。今はそうはいかなくなっているようだ。
短文の記事であるが、新潮社版全集第25巻の解題p.408に次の様にある。ドストエフスキーの編集する「市民」誌に『悪霊』を大作品と自分で書いているのは珍事だという「声」誌の批評が出たので、それを受けての文。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(生活の流れから)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
編集部から一言
副題(ニージニイ・ノヴゴロド定期市からの通信によせて)
1873年「市民」
ノヴゴロドの定期市では毎回、馬鹿騒ぎとなり乱飲放埓の放蕩三昧、強盗などの犯罪が起きている。何とかできないものか。外国人が見て呆れた。羽目を外すのはしょうがないのでなく、個人的な理性的な見解が求められる。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(編集者の感想 ニジニ・ノヴゴロド定期市に関する通信によせて。)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(編集部から一言 -ニージェゴロドの定期市からの通信に寄せて-)
編集部から
副題(ドイツからの通信『ドイツにおける大学授業のこと』によせて)
1873年「市民」
普仏戦争後のドイツの国民感情の昂揚は極めて大なるものである。最も好戦的な国民を破った。最高の政治的位置を獲得した。ドイツはロシヤの先生であったしこれからもそうであろう。先生を良く理解しなければならない。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(編集局から『ドイツの大学授業に関する感想』と題するドイツからの通信によせて。)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(編集部から-ドイツからの通信『ドイツにおける大学の授業についてのノート』に寄せて-)
旅の小景
1974年「サマーラ県の飢饉による難民救済のための文集」所収
旅と言っても汽車や船による旅で、馬の旅ではない。旅に出た者は興味ある対象である。初めは口をきかない。一旦誰かが口火を切ると調子に乗って喋り出す。鉄道利用時の法螺は(『白痴』のイヴォルギン将軍を思い出す、『作家の日記』1873年第15章「嘘についての一言」にもある)悪徳でなく、民族的善良さの自然の発露ではないか。
汽船には上客がいる。一等船室の客の中には高齢の貴族氏がいて、また上級の官吏、閣下と呼ばれる者がいる。更にそれより一段下の紳士連中がいる。上流婦人でも閣下夫人と同じ学校出なのに、こちらは結婚を誤ったと後悔している者など。
題の通り旅の点描なのであるが、小沼文彦は「これは評論ではなくて、『作家の日記』の中にちりばめられている文学作品に類するものである。」としている(筑摩版全集題20B巻、解説p.410)。新潮社版全集の文集名にあるとおり、飢饉救済のため提供した作品。文集名は河出版全集でも筑摩版全集でも「スクラッチナ」(義援の意味)としている。新潮社版全集題25巻解題p.409に発表年を1872年とあるが、1874年の誤り。
この作品の校正の件でドストエフスキーはゴンチャロフに書簡を2通出している。(1874年3月7日、3月下旬)
河出版米川訳全集第19巻、昭和46年(途上小景)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(ささやかな点景(旅の途中で))
最後のページ
1878年「市民」
ネワ川河口、ペテルブルグの市街地の北にあるエラーギン島で池からトリトン(ギリシャ神話のポセイドンの息子に当たる海神、下半身は魚)が現れ、人々を驚かせた。不埒に身体を動かしたので、婦人方は金切り声の笑い声を上げ逃げ出した。まもなく水中に消えた。この正体はなんであるか。イギリスの宰相とか色んな名が上がった。動物学者は見られず悔しがった。
ドストエフスキーが「市民」誌の編集を辞してから書いた唯一の文。小沼訳では「クジマー・プルトコーフとその親友の避暑地における散策より」という訳名になっている。新潮社版全集第25巻の解題p.409に「「クジマー・プルトコフの友」という署名で発表」とある。クジマー・プルトコーフとはある詩人が考えだした架空の名で、この名を使って多くの風刺詩等が発表されたと筑摩版全集第20B巻p.274の注(1)にある。河出版全集では本編は見つからなかった。
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(クジマー・プルトコーフとその親友の避暑地における散策より)
》以降は他人との共著、編集部としての立場からの文章である。(新潮社版全集の区分)《
文集『四月一日』の序
1846年にネクラーソフが発行したユーモア文集の序。「四月一日」とは四月馬鹿を指す。四月馬鹿で他人をかつぐ話を幾つか挙げ、最後にこの冊子は良心的であると結ぶ。他の作家の文とされていたが、終わりの方に我々は陰謀を企まない、それを誇りとしているとある。この言い方が『分身』に何度も出てくるので、ドストエフスキーの関与が認められている。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
名誉心の夢にふけるのはいかに危険であるか
副題(散文まじりの詩で書かれた、まったく本当らしくない茶番劇。プルジーニン、ズボスカーロフ、ベロピャートキン一同作。)
1846年、文集「四月一日」所収
ネクラーソフ、グリゴローヴィチ、ドストエフスキーの三人の執筆による合作というか連作。
役人ピョートル・イワーノヴィチ・ブリノーフの生活を綴る。ドストエフスキーはこのうち第3章と第6章を執筆した。第3章で主人公は夢を見る。若い娘の夢、口ひげをはやした男の夢、最後は役所で自分が格下げされたという夢を見る。第6章は、無様な姿を部長に見られた主人公は役所に登庁せず悩んでいる。空想する。自分は勤務優秀だ、その証明で退職して小ロシヤの領地管理人になる。しかし管理人になるためにはドイツ風の名が必要なのに自分はロシヤの名だ。役所をやめるのは良くないと分かり、空想から醒め役所に向かう。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(名誉心の夢にふけるのはいかに危険であるか 副題(散文まじりで書かれた完全にほんとうらしくないファース、-ブルジーニン、ズボスカーロフ、ベロピャートキン合名会社作))
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(功名心の夢にふけるのはいかに危険であるか 副題(散文まじりの韻文で書かれた、まったくありそうもない道化芝居(ファース)。ブルジーニン、ズボスカーロフ、ビェロピャートキン合名会社制作))
土壌主義宣言
ドストエフスキーに『土壌(または土地)主義宣言』という名の著作はない。これは『政治論』と同じく米川正夫の命名(米川は土地主義宣言を使った)である。雑誌予約募集広告などをまとめその内容から『土地主義宣言』と名づけた。新潮社版全集の染谷訳では『土壌主義宣言』とした。先行訳に批判的な小沼訳ではまとめず、個々の記事を年代順に収めている。
以下の6篇を含む。「雑誌《時代》の予約募集広告」「編集部より」「文学・政治雑誌《時代》1862年度の予約募集広告」「雑誌《時代》1863年度の予約募集広告」「《モスクワ報知》の攻撃に対する《時代》編集部の回答」「雑誌《世紀》1865年度の予約募集広告」
初めの1861年度の「時代」募集広告ではロシヤのおかれてきた状況を概観する。ピョートル大帝の改革はロシヤの上層部、教養階級のみを対象とし、国民は従来のまま放置されてきた。農奴解放等の改革で国民間の分離も終わりつつある。西欧派でもスラヴ派(改革を拒否する保守反動)でもなく、我々自身の土壌から国民精神の中から国民的源泉から採られた形式を創り出すべきと述べる。
ドストエフスキーは西欧派との対比でスラヴ派に属するとこのサイトでも述べてきたが、改革を排斥する反動のスラヴ派でなく土壌主義であるという意味である。
土壌主義の考え方は『ロシヤ文学論』(1861)第5章「最近の文学現象」でも述べている。また西欧派とスラヴ派については、翌年の『理論家の二つの陣営』でも詳しく書いている。
「《モスクワ報知》の攻撃に対する《時代》編集部の回答」は「時代」誌廃刊にからむ文章である。ポーランドは各国に分割されていた。そのポーランドで1863年に反露の暴動が起きた。「時代」誌1863年4月号にストラーホフのこの問題に関する論文が載った。その論文を「モスクワ報知」は親波反露的と攻撃した。ドストエフスキーがそれに反論するため書いた文章であるが、掲載許可が降りず「時代」誌は廃刊の憂き目を見た。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(土地主義宣言)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年に
「雑誌「時代」誌予約購読者募集広告」「「時代」1862年度予約購読者募集広告」
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年に
補遺I「編集部より」、補遺II「雑誌「時代」1863年度予約購読者募集広告」「M・M・ドストエフスキーの家族によって刊行される月刊綜合雑誌「世紀」発行について」
なお筑摩版小沼訳全集では「《モスクワ報知》の攻撃に対する《時代》編集部の回答」が見つからない。
カサノヴァ『回想録』の一挿話
副題(-ジャック・カサノヴァのヴェネツィアの牢獄(ブロン)幽閉と奇蹟的脱走)
1861年「時代」
カサノヴァ回想録の一番有名な牢獄脱出の部分が「時代」誌に載せられた。カサノヴァはロシヤではほとんど知られてないとまず書き、カサノヴァとその回想録がどういうものかを述べている。
30巻全集の注で回想録中のマンシイ神父と、スヴィドリガイロフやスタヴローギンの外貌の共通性を指摘しているとのこと。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(ジャック・カサノヴァの終章 ヴェニスのプロンブ脱走奇譚)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(ジャック・カサノヴァの幽閉とヴェネツィアの牢獄からの奇蹟的脱走)
ポーの三つの短編小説
1861年「時代」
「時代」誌にポーの短篇小説が3作(『黒猫』『告げ口心臓』『鐘楼の悪魔』)翻訳されたのでその序。この当時までにポーの小説は10篇ほど翻訳されていた。(筑摩版全集第20A巻、p.271の注)ホフマンとの比較でポーを論じる。ポーは幻想的というより気紛れな作家であり、その想像力によって創作をいかにもあったように描く。題名は挙げていないが、『ハンス・プファールの無類の冒険』『盗まれた手紙』『モルグ街の殺人』『黄金虫』等を例示する。ポーの幻想性は物質的でありアメリカ人らしい。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(エドガー・ポーの三つの短編)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(エドガー・ポーの三つの短篇)
ラスネール裁判事件
1861年「時代」
ラスネール(1803~1836、仏の詩人、殺人犯)の翻訳記事の序。著名な刑事訴訟事件は読者の関心を引くだろうと述べ、ラスネールを批判している。
なおラスネールの回想録は平凡社から出版されている。犯罪記録というより近代人の内面告白といった本。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(ラスネル事件)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
ストラーホフ『シラーについて』に寄せて
1861年「時代」
ストラーホフがシラーをあまり評価しないと書いたのでその反論として書いた。以前よりロシヤではバルザック、ユゴーなど西欧の作家たちをバイロンを除けば、あまり評価してこなかった。これはベリンスキーのせいである。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(ストラーホフの『シルレルについて』への付記)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(論文『シラーについての一言』への付記)
ユゴー『ノートルダム・ド・パリ』翻訳への序言
1862年「時代」
『レ・ミゼラブル』が公表された年であり、30年前の『パリのノートルダム』の露訳が出た。その翻訳への序言である。「ヴィクトル・ユゴーはたしかに、十九世紀のフランスに現われた最も力強い才能である」と称賛するユゴー論になっている。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(ノートル・ダム・ド・パリ)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(V・ユゴーの長篇小説『ノートル・ダム・ド・パリ』翻訳掲載に際しての序文)
希望
1873年「市民」
1月号に編集部言明という形で発表。わが国の定期刊行物はロシヤの醜聞、悪いところばかり載せている。これほどひどい国ならニヒリストにならずにいられようか、と思わせるほどである。本誌は社会的共感に値する現象や社会に奉仕する人々についての物語を多く発表したい。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
1860-1861年度の美術アカデミー展覧会
1861年「時代」
展覧会に出品された絵画を論じる。初めに取り上げている囚人隊の絵画について、徒刑経験のある者ならではの記述があるとしてドストエフスキーの著作とされている。本論文は絵画及び舞台芸術についてかなり詳細な考察があり、いかにも専門家の筆になる論述に見える。これより12年後に書かれた『作家の日記』1873年第9章でも展覧会の絵画を論じている。ロシヤの絵画は文学に及ばないなどと書き、絵画に対する関心は伺えるが、美術に関する専門性は本論文ほどでない。30巻全集では疑義を残しながら本文に組み入れられているそうだ。戦前の13巻全集では付録扱い。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(1860-1861年度、美術アカデミー展覧会)
N・V・ウスペンスキーの短編小説
1861年「時代」
ウスペンスキーが短編小説を単行本で出した。ウスペンスキーの作品を批判的に評する。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(N・V・ウスペンスキイの短編)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(N・V・ウスペンスキーの短篇小説)
一八五四年のヨーロッパの事件に(詩)
ドストエフスキーには珍しい詩で執筆は1856年である。当時シベリヤのセミパラチンスクで兵役についていたドストエフスキーはロシヤ本土に帰りたく、恩赦目的で新帝であるアレクサンドル二世に捧げる詩を書こうと思いたった。友人のヴランゲリ男爵あて1856年5月23日の書簡で、清書して皇帝のもとに届くよう取り計らってもらえないか頼んでいる。結局叶わなかったようで、没後1883年に「市民」誌に掲載された。
1854年は前年から始まったクリミア戦争(1853~1856)に英仏が参戦した年である。内容は敵方についた英仏を批判し、ロシヤの使命を謳い上げる。
河出版米川訳全集第20巻、昭和46年(詩--1854年のヨーロッパ事件に--)
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年(1854年のヨーロッパの諸事件に寄せて)
抜粋と所見
1861年に執筆、当時の発表はない。30巻全集で初めて活字になった。
二つの話題がある。人間には昔からの習慣を美化する者、また新しいものの魅力に惹かれる者がいる、つまり伝統指向と革新指向があるという話題。
もう一つの話題は、ある歴史書に対する書評が出て、その書評を要約し反論しようとしたメモ。歴史書とはウストリャーロフ『ピョートル大帝治世史』第6巻(1859)で、書評したのは歴史家セメーフスキイ。ピョートル大帝とアレクセイ皇太子の不仲(処刑、獄死した)についての論である。
新潮社版全集第25巻の解題では、歴史書書評の要約と所見についての解説しか書いていない。伝統、革新の議論は筑摩版全集第20B巻のあとがきに「オプトゥーヒン(パーヴロフ)の論文「ロシヤ文学における東と西」」とある。
新潮社版全集第25巻、1980年、染谷茂訳
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年(抜き書きと注釈)
》以上、新潮社版全集第24巻、第25巻所収の評論の要約である。
ただし筑摩版小沼訳全集では30巻全集を利用しているので、筑摩版全集でのみ収録されている文章を以下に書く。《
N・N・ストラーホフの論文「論争について一言」への書き入れ
1861年「時代」
ヴォルテールは一生の間、呼子を吹き鳴らし続けた、何も反響がなかったわけでないなどと述べる、この全集で4行の文。
筑摩版小沼訳全集第20A巻、昭和56年
『災難は逃れがたい』のヴァシーリイェフの演技について
1891年「北方通報」
1864年執筆。オストロフスキーの戯曲『災難は逃れがたい』は1863年発表、翌年初演。この劇のクラースノフ役のヴァシーリイェフの演技が素晴らしいという評判。ドストエフスキーも観てこの役者を評価している。文章のほとんどはこの戯曲の解説である。
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
D・V・アヴェールキイェフの論文『二人のペテルブルグ人の告白』に対する注
1864年「市民」
スイスの全寮制の学校で3年間勉強している13歳のロシヤ人の男子に会ったら、ロシヤ語をほとんど理解していなかった。笑っていられない。
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
A・A・ゴロヴァチョーフの古典教育についての論文に関する覚え書き
1907年雑記「昔のこと」
古典教育と実科教育のうち、古典教育よりもロシヤの認識(歴史、言語、国民性など)にかかる教育が必要である。ピョートル大帝の改革で専制政治のための不幸なヨーロッパ原理を取り入れて、ロシヤの国民に対する本来の思想を失ってしまった。
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
わが国の僧院(雑誌「談話」一八七二年)
1873年「市民」
雑誌「談話」にロシヤの僧院に国家(実際は国民だが)が負担する費用の数字が載っていた。司法機関や国民教育の負担額と同じである。この負担について、中には感心しない修道僧がいるので批判が出た。
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
イズマイロヴォ村の火事
1873年「市民」
モスクワ近郊の村で火事が起きた。消火用具等は酒の飲み代になって消えてしまっていた。よその土地への移住も居酒屋から逃げ出そうとする気がある。酒だけが気晴らしとは大昔からの事である。民衆を楽しませる、他の方法があってもいいのではないか。
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
ねだり上手
1873年「市民」
ある県に赴任するにあたってそこの知事あての、有力者による紹介状を欲しがっている青年がいる。知事が世話になった将軍がいて適任なのだが、気難しい将軍なので頼みにくい。
そこに「ねだり上手」の知人が来た。頼んでみたら明日にも貰ってくると返事。実際に貰って来たのでその秘訣を聞く。将軍に面倒な頼み事があると言う。てっきり金の無心だと相手は思う。最後に紹介状を書いてくれというと喜んで書いてくれた。
筑摩版小沼訳全集第20B巻、昭和57年
(続く)
創作以外、『作家の日記』、書簡
ドストエフスキー全体のトップへ