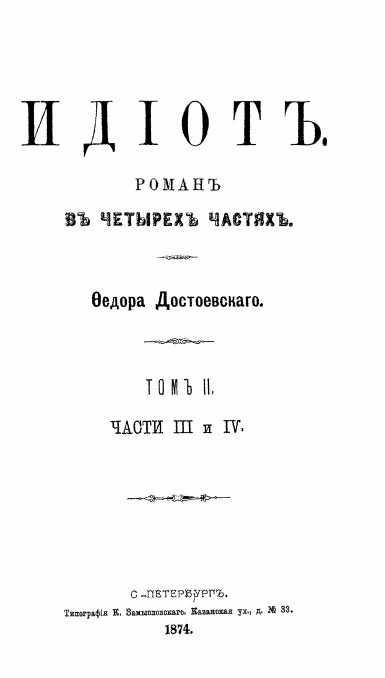[ムイシュキンの白痴ぶり]
小説の主人公はムイシュキン公爵である。ただドストエフスキーの他の長篇小説でもそうだが、主人公級の重要人物が多く登場する。レフ・ニコラエヴィチ・ムイシュキン公爵(望月哲男訳、中山省三郎訳ではムィシキン、小沼文彦訳、北垣信行訳、亀山郁夫訳ではムイシキン、米川正夫訳、木村浩訳ではムイシュキンである)について大抵の読者はムイシュキンが馬鹿だと言われる、しかしながら美しい人間であるとの知った上で小説を読み始めるのではないか。それで頭からムイシュキンをそういう者だと理解して読む。ムイシュキンを虚心に見ていくとどうか。
小説の初め、汽車の中でロゴージンと役人レーベジェフに会う。その際、ムイシュキンが自分は神経の病でありスイスで四年間治療してきたと話す。まだ完治していないと言う。ここの列車内の会話でも、ペテルブルクに着いてからのエパンチン将軍家の会話でも、ムイシュキンを馬鹿だとは思わないだろう。ムイシュキンはロゴージンにすっかり気に入られる。エパンチン将軍家でも好意を持たれる。
邪気のないムイシュキンの態度にみんないい人だと思うのである。ただ率直な物言いは、周囲の状況等を勘案せず、常識がない、馬鹿だと思われるにつながる。
それにみんなムイシュキンがスイスで治療してきたと知っているので、馬鹿だと先入観がある。
以下はエパンチン将軍家でムイシュキンに対して言われたidiotである。
「でもあの公爵、ひょっとしてお馬鹿さん(イディオット)どころか、たいしたくわせ者かもしれないわ」エパンチン将軍の長女アレクサンドラの言葉(『白痴』1、望月哲男訳、河出文庫、2010年、p.113)
「まったく何も分かっていないんだから・・・この白痴(イディオット)が!」秘書ガヴリーラ(ガーニャ)のつぶやき(同上、p.165)
「・・・ああ手に負えない白痴(イディオット)だ!」ガヴリーラの憤懣(同上、p.186)
以上、「お馬鹿さん」も「白痴」も原語はidiotで、題名と同じである。ガヴリーラの言は日常語なら馬鹿が、とか馬鹿野郎の方が合うと思うが、題名と同じ言葉を使っていると示したくて、白痴を使ったのではないかと想像する。
ムイシュキンは知能の点では劣っていない。それどころか鋭い洞察力を持つ。加えて予言能力さえ持っている。小説の初めの方、エパンチン将軍家で、ガヴリーラの質問、ロゴージンはナスターシャと結婚するだろうか、にムイシュキンは次の様に答える。(第1篇第3節) 「そうですね、結婚するだけなら、もう明日にでも結婚すると思いますよ。でもいざ結婚したら、おそらく一週間で相手を斬り殺してしまうかもしれませんね。」
(『白痴』1、望月哲男訳、河出文庫、2010年、p.75)
この時点ではまだムイシュキンはナスターシャに会っていない。ロゴージンから話を聞かされ、写真を見ているだけである。
ムイシュキンはキリストになぞらえられる。キリストは多くの奇蹟を行なった。現代のキリストなら予言できても不思議でない。
もう一つムイシュキンの特異姓は恋愛感情に関してである。後に書く。
[恋愛模様]
ナスターシャ・フィリポヴナ・バラーシコワは女主人公といっていい存在である。出自は貴族ながら幼いうち両親を亡くし、隣人トーツキイに扶養される。教育も受け長じて贅沢もできるようになる。ただ奢侈には興味がない。少女時代にトーツキイの囲い者にされた。この過去を痛く恥じ、世の中を呪っている。トーツキイが結婚しようとすると邪魔せずにはおかない。第4篇第8節で、ムイシュキンの愛を巡って、ナスターシャと令嬢アグラーヤは対決する。ここの部分は山場の一つであるが、アグラーヤによる「謎解きナスターシャ」といった趣になる。アグラーヤはナスターシャに向かって次の様に言う。
「・・・あなたという人は、ただひたすらご自分の恥辱だけを、そしてご自分が辱められた、傷つけられたという絶え間ない思いだけを、愛することしかできない人だからです。」 (『白痴』3、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.311)
正直、ナスターシャは自分の恥辱によって動かされているのかと思わせるような行動をとるのが本小説である。
ナスターシャは第1篇の終わりの方、自宅の夜会で、いきなりムイシュキンから求婚される。過去の恥辱によって劣等感の塊になっていたナスターシャは、ムイシュキンから純潔なあなたを受け入れたい、あなたから名誉を与えてもらう、愛している、あなたのためなら死ねると言われる。女なら誰でも感激するだろう。
更に文無しと思われていたムイシュキンが巨額の財産(後にそれほどでないと判明する)を相続すると分かる。ナスターシャは公爵夫人になれるのである。この夢のような話を振って、自分を熱愛しているものの、粗野な商人に過ぎないロゴージンと逃げる。
このあまりに馬鹿げた振る舞いに同席者の一人はナスターシャを切腹する日本人に例える。切腹とは自殺という自虐の最たる行為をし、それでもって自分の敵に復讐した気になる奇行と理解しているから。ここでナスターシャは誰に復讐しているのか。金で解決しようとしているトーツキイ、金を目当てに結婚を考えているガヴリーラ、ナスターシャを情婦にしたい気でいるエパンチン将軍など、自分を取り巻く俗物どもに対してである。もちろん自分があまりに善人のムイシュキンにふさわしくない、ムイシュキンを不幸にしてしまうと感じたため逃げたのである。
第2篇第3節でムイシュキンはロゴージンと再会する。ナスターシャの夜会後の会話になる。ロゴージンと逃げ出したものの、式の間際になって逃げ出し、ムイシュキンのところへ行く。その後また逃げ、ロゴージンへ行くがまたそこから逃げる。ずっと後になって小説の終わりの方、第4篇第10節、ムイシュキンとの婚礼直前にロゴージンを見つけたナスターシャは「わたしを助けて! 連れて行って! どこでもいいから、いますぐに!」(『白痴』3、河出文庫、p.367)と叫び、去っていってしまう。いくら女が気まぐれだからといって、ナスターシャの行動はひどすぎないか。
アメリカ映画『卒業』(1967)でダスティン・ホフマン演じる青年は、映画の最終場面、好きな女が他の男と結婚しようとしている結婚式から女を連れて逃げ去る。この場面は有名でネタにしばしばされる。その百年前、『白痴』ではもっと頻繁に結婚直前逃走劇をやっている。
ムイシュキンを真に愛しているナスターシャは、ムイシュキンに幸せになってもらいたく、アグラーヤに手紙を書き、ムイシュキンとの結婚を促す。自分は身を引き、愛する人は幸せになってもらいたい・・・これは昔の日本のメロドラマを思わせる筋書きではないか! 正直なところ、そう理解するとナスターシャの行動は日本人的に見える。ナスターシャの行動は切腹的と言われた。ナスターシャを評したアグラーヤの言、自分の恥辱だけを愛している女、これはドストエフスキーに良く出てくるマゾヒズム性である。そうなるとこの辺りで日本人の感性とドストエフスキーは地下でつながっているのか。日本人のドストエフスキー好きの理由の一端はこう理解できるのか。ここまで書いて、そんな思いがしてきた。
パルフョーン・セミョーノヴィチ・ロゴージンはナスターシャをムイシュキンと張り合う。ロゴージンは熱狂的にナスターシャを愛しているが、そのナスターシャはムイシュキンを愛しており、ロゴージンには一顧だにしない。
ロゴージンはムイシュキンと義兄弟の契りを交わした後、ムイシュキンを殺そうとする。たまたまムイシュキンは癲癇の発作を起こして、刺されずに済んだ。ナスターシャを自分のものにすべく恋敵を排除しようとしたのである。しかしムイシュキンを殺してもナスターシャは自分に振り向いてくれないと分かる。
全く望みがないと知ると、可愛さ余って憎さ百倍で、あるいは他の者に取られないよう独占欲でナスターシャを殺すしかない。
ロゴージンの愛情は、ドミートリイ・カラマーゾフが弟アリョーシャに言う次の言葉を思い出させる。
「惚れるってことは、愛するって意味じゃないぜ。惚れるのは、憎みながらでもできることだ。」(カラマーゾフ第3篇第3節、新潮文庫、上、原卓也訳、昭和53年、p.194)
もっともロゴージンはドミートリイ系の人間でない。ドミートリイのような純粋さはない。もっと暗い。スヴィドリガイロフの系統である。『白痴』の有名な黒澤明の映画でロゴージン役は三船敏郎が演じているが、三船のイメージを(持っている人は)ロゴージンにかぶせるべきでない。
ナスターシャとアグラーヤの対決の場面で、最後にナスターシャはアグラーヤに向かって叫ぶ。(第4篇第8節)
もし望みならムイシュキンに、アグラーヤを捨てて自分と結婚しろと命令してやる。ロゴージンなど追い払ってやる。出て行け、ロゴージン!
これがロゴージンをして殺害する気にさせた、直接のきっかけになったかと思うほどである。
アグラーヤ・イワーノヴナ・エパンチナはエパンチン将軍の三女であり、ムイシュキンのもう一人の恋愛相手である。ナスターシャに比べそれほど話題にならない。
アグラーヤはカラマーゾフの最初の方に出てくる、フョードルの最初の妻、アデライーダ・イワーノヴナ・ミウーソワと同じ型の女である。そのアデライーダは名門貴族の出で美貌に恵まれながら新しい思想に興味を持ち、おかしな結婚をロマンスと空想し破滅する。
ムイシュキンとアグラーヤの関係は次の様に進む。
第2篇第1節で、ムイシュキンはアグラーヤに手紙を書く。ナスターシャが逃げ去った後である。あなたは自分に必要だ、どうしても幸せでいて欲しい、という内容である。ムイシュキンの意図は不明だが、恋文に読める。後に第2篇12節でアグラーヤの母親エリザヴェータ夫人にこの手紙の件で問い詰められる。第3篇第2節ではアグラーヤはみんなのいる前で、ムイシュキンに向かってあなたのような変な人とは結婚しないと宣言する。第3篇第3節で、アグラーヤとムイシュキンは決闘の話をし、アグラーヤは朝早くベンチで会いたい旨の手紙を渡す。第3篇第8節で、アグラーヤとムイシュキンの逢瀬がある。ガヴリーラが好きだと心にもない嘘をつく。ナスターシャからアグラーヤにムイシュキンとの結婚を勧める手紙をもらったと告げる。第4篇第5節で、ムイシュキンはアグラーヤに結婚の申し込みをする。
第4篇第6、7節は婚約お披露目の夜会である。ここでムイシュキンは恩人がカトリックに改宗したと聞いて驚愕し、饒舌になって熱弁をふるう。
普段物静かな人が突然感情を爆発させる場合がある。自分を振り返ると言いたい放題、やりたい放題しているわけではない。当たり前だ。しかしなぜか他人はその意思通りの言動をしていると思いがちである。喋らないのは喋りたくない、あるいは意見がないと解釈してしまう。実際はそうではない。だから何かの拍子に感情を露わにされると驚くのである。
ここでドストエフスキーはムイシュキンにカトリックへの攻撃とか、社会主義はカトリックが生み出したとか、自分の意見を代弁させている。
作者の代弁ではこれより前、第3篇第4節でレーベジェフにヨハネ黙示録からの引用で鉄道網の発達に留まらず近代物質文明への批判や、中世の飢饉による醜行なども言わせている。小説初めの登場では金棒引きの太鼓持ちにしか見えなかったレーベジェフがいっぱしの知識人のようになっている。
ムイシュキンの饒舌は、不注意で支那焼の花瓶を壊してしまうまで続く。夜会の前、アグラーヤはムイシュキンに向かって支那焼の花瓶でも壊したらと気まぐれ(?)で言う。(第4篇第6節)それが実現したのである。不器用さはムイシュキンが調子や要領のいい男でなく、真面目な人間であると思わせる効果がある。
このムイシュキンの失策は『赤と黒』でジュリアン・ソレルがやはり不注意で日本の花瓶を壊してしまう出来事を思い出すだろう。(第20章「日本の花瓶」)令嬢マチルドは汚い花瓶だったので喜ぶという話である。偶然だろうが東洋の花瓶の損壊で一致しているのは面白い。
アグラーヤはムイシュキンと婚約したものの、相手はナスターシャを好きではないかとの疑いがぬぐいきれない。それをはっきりさせるためナスターシャとの前でムイシュキンの気持ちを確かめる。これが決裂をもたらす。
ムイシュキンの愛し方

さてムイシュキンのナスターシャとアグラーヤに対する愛情である。
ナスターシャとアグラーヤの対決の後、第4篇第9節で、エヴゲーニー・パーヴロヴィチ・ラドームスキー(アグラーヤに気があり、後にナスターシャと知り合いだったと分かる青年)は、ムイシュキンに向かい、二人に対する愛情を確かめる。ここの部分は謎解き白痴の趣になっている。
ラドームスキーはムイシュキンに、ナスターシャとアグラーヤ共に愛しているのかと確認するとムイシュキンは肯定する。これを聞いてラドームスキーは驚き、何を言っているのかと叫ぶ。
読者は何と思うだろうか。男なんて浮気者さで済ますのか。ドストエフスキー自身も最初の妻、マリヤ・ドミートリエヴナが存命中にアポリナーリヤ・プロコーフィエヴナ・スースロワと交際し外国旅行までしている。
明らかにナスターシャとアグラーヤに対するムイシュキンの恋愛感情は違う。天上の愛と地上の愛、アガペーとエロス、どの言葉が適当か知らないが、二人に対して違う愛情で接している。「聖愛と俗愛」(1515)というティツィアーノの絵があった。
まずナスターシャに対しては憐憫を感じている。広い意味での愛であると言っても、恋愛感情とずれる気がする。大体ムイシュキンのナスターシャに対する態度はよく分からない。
会ってろくに相手を知らないうちに、いかに精神的に優れた存在か誉めそやす。ドン・キホーテは単なる村娘のアルドンサを、騎士が敬い愛を捧げる貴婦人ドゥルシネーアと思い込む。ドン・キホーテの頭がおかしいせいだが、ムイシュキンも思い込みでナスターシャに対しているのか。何度もナスターシャは精神がおかしいと弁解しているし、ラドームスキーに対してナスターシャは気が狂っているので顔が怖いと言っている。どういう意味か。
アグラーヤを振っておきながら、後から説明に行きたいなどと言っており、精神がまともかと思いたくなる。小説の初めにムイシュキンはロゴージンに向かい、病気なので女を全く知らないと答えている。色んな解釈があるらしいが、そもそもムイシュキンは異性愛が無理なのか。現代人の愛の不毛、といったらこれまた昭和時代の通俗小説か映画の宣伝文みたいに聞こえる。ただしアグラーヤへの愛は普通に見える。憐憫を恋愛より重きを置かなくては、とする考えなのだろうか。
創作ノートに次の有名な文がある。
この長篇には三つの愛がある――(三つのに傍点)
(一)情熱的で誰にも気兼ねしないひたむきな愛ロゴージン。
(二)虚栄心に基づく愛――ガーニャ。
(三)キリスト教的な愛――「公爵」。〈十二ページ〉
(筑摩版小沼訳全集第19B巻、1989年、p.144)
キリスト教的な愛だからムイシュキンは普通の恋愛と違うのか。
》良く分からないところ《
ナスターシャの悲劇については、エパンチン将軍家でムイシュキンは予言(第1篇第3節)しており、第2篇第3節でムイシュキンは、再会したロゴージンとの会話でその予想を繰り返す。(望月哲男訳河出文庫2ならp.77~78)更にナスターシャ自身がアグラーヤに宛てた手紙で、自分がロゴージンに殺されるだろうと言っているのである。(第3篇第10節、望月哲男訳河出文庫3ならp.75)
小説中3回も悲劇の予想が書いてあるのである。ナスターシャは覚悟していたらしい。読者はいつ起こるかと待ちながら読んでいるだろう。それにしてもムイシュキンは悲劇を予想しておきながら、なぜ何もしなかったのか。良く分からない。『悪霊』のところで書いたようにスタヴローギンやイワン・カラマーゾフは非常に良心的に見えるのにムイシュキンはなんだという感じになる。
この小説でムイシュキンはスイスから帰国し、ロゴージン、ナスターシャ、エパンチン将軍家、イヴォルギン将軍家などと会う。異者(よそ者)としてムイシュキンがやって来て事件が始まる。これは劇や小説の基本的な作り方の一つである。
ムイシュキンの出現は何をもたらしたか。主要人物の破滅である。
ナスターシャはムイシュキンがいなかったなら俗物のガヴリーラにしろ、野人のロゴージンにしろ、それらとの結婚で生を永らえたはずである。ロゴージンも凶悪犯罪で刑に服せずすんだはずだ。ムイシュキンをキリストになぞらえる読み方がある。しかしこれでは救世主どころか疫病神ではないか。聖書のキリストの次の言葉を思い出した。
「わたしが来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和でなく、剣をもたらすために来たのだ。わたしは敵対させるために来たからである。」(マタイ福音書10-34以下、新共同訳)
カラマーゾフに出てくる大審問官が『白痴』を読んだら、「それみろ、キリストなんか現れたらろくなことにならない」と言ったのではないか。
以上書いてきたが、解釈としては的外れであろう。一方的にどちらが害を及ぼしたかでない。恋愛であって対等関係であり、組織にあるような上下関係ではない。ムイシュキンが善人だから俗世間に破滅させられた、とよくある説明も賛成できない。
人間関係は相互依存であり、どちらかがいい、悪いで判断する小説とは思っていない。
[イッポリートの告白]
『白痴』は恋愛小説のような態をなしている。昔はドストエフスキーと言えば思想を読むと決まっていた。それで『白痴』中、何やら深刻な思想を語っているかのような「イッポリートの告白」が注目されていた。専ら恋愛小説と読んでいる者は「イッポリートの告白」なぞ無視である。イッポリート・テレンチエフは18歳の青年ながら肺病に侵され数週間の余命である。イヴォルギン将軍の情人になっている未亡人の息子である。小説では第2篇第7節でムイシュキンが相続した財産の正当な相続人を名乗って押しかける、一団の一人として初登場する。
このイッポリートは人間として非常に嫌な男に描かれている。他人に嫌がらせばかりしている。何しろ「人間はまさにお互いいじめ合うように作られているのだから」(『白痴』2、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.461)という哲学の持ち主である。「完全に醜い人間」を意図したのかと思ってしまった。
通称「イッポリートの告白」は死を直前に控えたイッポリートの意見表明、心情吐露であり、一種の遺書である。第3篇第5節以下にあり、正式には「わが不可欠なる弁明」といい、題辞として「後は野となれ山となれ」がついている。
イッポリートの不治の病は、日本でも戦後治療薬が開発されるまで多くの若者の命を奪っていた。
なぜ若い自分が死ななくてはならないのか、長生きして下らない人生を送っている者がいるのに、いっそ死んでやる、などと内容を要約したら身も蓋もない。
色々経験など挙げて自分の論を進める。カフカの『変身』みたいな夢や、ロゴージンの幻影を見たりする。ロゴージン宅でホルバインの「死せるキリスト」の絵を見る。赤ん坊が死んだ同じ建物に住む惨めな男(幼い娘を失ったドストエフスキー自身か)に対して自業自得だと笑うのでさすがに追い出される。また偶然出会った医師の一家を助ける話にページを割いている。
イッポリートは自分が死んで長生きする連中に悪態をつく。「この先60年もの人生を授かっていながら、奴らが不幸で生きるすべを知らないからといって、いったい誰のせいだというのか?」(同上、p.455)
この後、知り合いの貧しく不幸に見舞われた男を「いったいなぜこの男はみずからロスチャイルドにならなかったのか?」(同上、p.456)と非難する。ドストエフスキーにとって富豪の代名詞がロスチャイルドであったようだ。(『未成年』のアルカージイ)もっとも本作のガヴリーラ・イヴォルギンはやはり金持ち志向だが、ロスチャイルドという言葉を使わずユダヤの王になりたいと言う。(第1篇第11節)
自分の信念は死を宣告されても変わらない。コロンブスの挿話を持ち出す。コロンブスが幸福だったのはアメリカを発見した時でない。探し求めていた時だ。結果より過程が重要だと言ったら平凡になるが、『地下室の手記』でも同じ意見が書いてある。
「この世で人類が志向している目的というものはすべて、この達成への絶えざるプロセスにのみある。言い換えれば生そのものの中にあるのであって、目的自体の中にはないかもしれない。」
(『地下室の手記』、光文社古典新訳文庫、安岡治子訳、2007年、p.68)
この後、目的と言ったら二、二が四といった公式でそれは死の始まりではないか、と続ける。これは少し分かりにくいが、後で述べる自然の法則を解明する科学が信仰の終わり、ドストエフスキーにとって死につながるのに対応しているのであろう。またこの当時、理想の社会とされた社会主義(目的)がドストエフスキーにとって理想でも何でもなく、生きていく、その過程自体が重要だとの考えでもある。
「墓の中の死せるキリスト」

ホルバインの「墓の中の死せるキリスト」(1521)を、ドストエフスキーは『白痴』執筆前、1867年8月にバーゼルの美術館で見て衝撃を受けている。全く死骸そのもので腐敗を始めているかのように見える絵である。
この死せるキリストの複製がロゴージン宅にあって、ムイシュキンは「あの絵のおかげで信仰をなくす人もあるかもしれないよ!」(第2篇第4節、『白痴』2、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.89)と言う。これより前、エパンチン将軍家でムイシュキンはギロチンの絵を描いたらと次女アデライーダに勧める。(第1篇第5節)その際、バーゼルで同じような絵を見たと言っている。名は挙げていないが「死せるキリスト」であろうとされている。
イッポリートもロゴージン宅でこの絵を見て次の様に思う。あまりの生々しい死骸に、こんな死体を見せらせたら、誰が復活すると信じられよう。
キリストは死後3日目に復活したと聖書にはある。
ここでドストエフスキーの小説を読む限り、キリスト教の信仰は不死の信仰と表裏一体とのように見える。ヨハネ福音書3-16に次の文がある。「神はその独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」神の独り子はイエス・キリスト。ヨハネ福音書をドストエフスキーは高く評価していた。別ページ「文豪に影響を与えたと思われる作家」を参照。
フョードル・カラマーゾフが息子イワンとアリョーシャにする質問(カラマーゾフ第3篇第8節)を参照。二つあり二人から反対の回答を得る。また『作家の日記』1876年12月第1章第4、5節で自殺の多さを人間の霊魂の不滅の信仰を信じていないからだと言っている。
キリストは聖書で多くの奇蹟を行なっている。死者を甦えさせた(『罪と罰』でラスコーリニコフがソーニャに読んでくれと頼んだ話)などである。しかしそのキリスト自身がこうやって無残な敗北をしているのに、どうして自然の法則を克服できるだろう、と問いかける。不死がキリストでさえ無理なようでは信仰など保てない。
『悪霊』のキリーロフはピョートルに向かって次の様に言う。キリストこそ最高の人間で、奇蹟と言えるもので今後も現れないだろう。
「もしそうなら、つまり自然の法則がこの人(この人に傍点)にさえ憐みをかけず、自身の生み出した奇蹟をさえいつくしむことなく、この人をも虚偽のうちに生き、虚偽のうちに死なしめたとするなら、当然、全地球が虚偽であって、虚偽の上に、愚かな嘲笑の上にこそ成り立っているということになる。つまりは、この地球の法則そのものが虚偽であり、悪魔の茶番劇だということになる。」(『悪霊』下、新潮文庫、江川卓訳、昭和46年、p.438)
イッポリートのホルバインの絵の感想は次の様である。
「この絵を見ているうちに(中略)自然とは一種の巨大な、最新式の機械なのだと思えてくる。その機械が、かけがえのない偉大な存在を意味もなく捕まえ、無造作かつ無感覚に吞みこんでしまった――しかもその犠牲者が誰かといえば、その存在ひとつが全自然とその法則のすべて、この地球全体に値するような人物であり、ひょっとしたら地球そのものが、ただただこの人物を出現させるために作られたのかもしれないというほどの人物なのだ!」
(『白痴』2、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.488~489)
ホルバインの絵にみられるように自然の法則がキリストを、復活や不死が無理な単なる死体にした。信仰は自然の法則に打ち勝てないのか。これはドストエフスキーが度々述べる科学や経済の発達した西欧では信仰が失われている、につながっていくとも言える。
イッポリートのその他の言動
イッポリートは偶然知り合った医師一家に尽くしてやり恩人となる。この話に、イッポリートは嫌味のように見えて実際は心が優しいとの解釈があるらしい。イッポリートは友人相手に、善行をしたくなったと思っても残りの時間が限られているからやれることしかできないと語る。
小説技巧的には次の様に思える。殺人犯ラスコーリニコフは悲運に見舞われたマルメラードフ一家を何くれと助ける。嫌な男イッポリートに親切な行為をさせている。こうした書き方は登場人物をして厚みを持たせる、立体的にさせるのである。実際の人間らしくしている。
イッポリートは残り少ない命なのでどんな犯罪をしようが、罰せられない、裁判など意味はないと笑っている。好き勝手に十人ばかり殺そうが世の中で一番ひどい悪事をしようが関係ないと。ここを読むと現代の我々は笑えない。20世紀になってから、実際に大量殺人をしてその後犯人が自殺した例を多く知っているからである。我が国の津山事件からしてそうだし外国でも例が結構ある。
イッポリートはロゴージンの幻影まで見るようになる。「生がこれほどまでに奇妙な、ぼくを愚弄するような形をとる以上、このまま生きているわけにはいかない。」(同上、p.494)
座して死を待つより自らの意思でけりをつける。キリーロフの自殺に比べたら分かりやすい。
美は世界を救う、どうか僕たちのそばを通り過ぎて・・・
ムイシュキンの言葉で、イッポリートが「告白」を読む前に周囲の者たちに話した「美は世界を救う」という文句は有名らしい。
「公爵は、世界を救うのは美だと主張しています! でもぼくの主張はこうです。――そんなふざけた考えが頭に浮かぶのは、この人がいま恋をしているからだと。」
(『白痴』2、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.431~432)
また「告白」よりずっと後、ムイシュキンとイッポリートの最後の会話でのムイシュキンの答え(第4篇第5節)もしばしば言及される。
イッポリートはどんな死に方をするのが一番いいのか、いわゆる気高い感じをだすには、とムイシュキンに教えを乞う。その答えである。
「どうか僕たちの脇を通りすぎて、そして僕たちの幸せを許してください!」
(『白痴』3、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.216)
この答えを聞いてもイッポリートはそんなことだろうと思ったと笑うだけである。イッポリートは嫌味や嘲笑によってしか自分を表現できない痛々しい人間である。
よくムイシュキンとロゴージンが対照的と言われるが、イッポリートもまたムイシュキンと対照的な存在といっていいのではないか。
自殺し損ないについて
「告白」を読んだ後、イッポリートは周囲の者たちと言い争いをし、遂に自殺を決行する。といっても決行したつもりでいたのに不注意で雷管を入れ忘れ、拳銃は発射しない。この事実が明らかになるや否や、イッポリートは嘲笑の的になり赤っ恥をかく。泣いて、つい不注意で忘れたのだと弁明して回る。
ずばり言おう。『白痴』を読んだ者は他の部分を忘れても、「告白」の中身など全く忘れてもこのイッポリートの自殺失敗は覚えているだろう。一体この失敗はどういう意味があるのか。『白痴』最大の問題ではないか!と言ったら言い過ぎかもしれないが、ともかくこれほど読者の記憶に残る出来事を論ぜずして、何が『白痴』論だ、・・とは言わない。
ドストエフスキーは時々登場人物に意地悪をする。この小説でも嘘を平気でつくイヴォルギン将軍は、ナスターシャに話した経験を新聞で読んだと指摘され恥をかく。(第1篇第9節)そのイヴォルギン将軍がムイシュキンに語る、幼い日、ナポレオンの小姓になったという話(第4篇第4節)は本当に面白い。嘘と言うより法螺であり、こういうところを読むとドストエフスキーには本当に感心させられる。
よくドストエフスキーと限らず、小説中の名言と思われる文句を集めている人がいる。そういう人たちは小説を人生論とも読んでいるのであろう。
名言を集める趣味はないが、小説中に感心する部分がある。『罪と罰』で挙げた、予定もしなかったリザヴェータが現れたため、余計な殺人まで犯す。考えていなかった事態の出現で困る経験なら誰にでもある。
イッポリートの自殺も同様なところがある。一世一代の大芝居を打って見栄を切る気でいたのに、大失敗で恥をかくだけに終わるのである。イッポリートの例は極端であるが、程度を変えれば見聞きしたり経験したりしている。
ドジの真意は分からない。生意気なイッポリートを懲らしめるつもりか、単に読者を面白がらせるサービスだったかもしれない。読む者がどう思うかで良いのかもしれない。
[『白痴』の評判、作家の評価]
『白痴』でドストエフスキーがどう意図したかは上に述べた。それでは当時の『白痴』の評価や評判はどうであったか。まず執筆後、間もない頃に姪ソーニャ宛てに送った手紙で自分の評価を述べている。
「・・・ぼくはこの長編に満足していません。といってやはりこの長編を否定はしませんし、不首尾に終った構想をいまだに愛してはいるものの、この長編はぼくが言い表したかったことの、十分の一も表現しなかったからです。」(新潮社版全集第21巻、p.163、原卓也訳、1869年1月25日)
単に芸術家として満足な出来栄えか、だけの問題ではない。ドストエフスキーは本作が『罪と罰』なみに評判が良くて単行本化し、それで多くの収入を得たいと期待していた。借金から逃れてロシヤから欧州まできたのである。借金を返済しロシヤへ帰れるよう願っていた。
親友マイコフからの手紙で、掲載当初、評判がいいと聞き有頂天になっている。
「・・・貴兄のお手紙を頂戴するまでは、長編の完全な失敗とぶざまさを思って、完全な絶望状態に陥っていました。ですから、作者としての悲しさどころか、すべての希望が泡と消えてしまったと確信していたのです、この長編一つにすべての希望がかかっていたのですから。貴兄のお手紙は私をどんなにか喜ばせたことでしょう。(中略)
そんなわけで、あの長編が成功したという知らせは私をすっかり喜ばせてくれました。いまや私はすっかり元気を取り戻しました。」(新潮社版全集第22巻、p.179、江川卓訳、1868年3月2日)
公表当初、小説の評判を聞かせてくれとロシヤの友人に頼んでいた。マイコフからの手紙で凡ての知人から『白痴』の最初の部分は評判がいい、「声」紙は『罪と罰』よりよいと書いていると知らせてきたのを受けた返事。
後に執筆途中、嫌気がさしているとマイコフに書いている。
「長編は嫌気がさすくらい気に入りません。恐ろしいほど根をつめて仕事をしましたが、だめです。精神状態が不健康なのです。いま第三編(引用者注:現在の第3篇でなく、第2篇)に全力を注いでいます。もしこの長編をもち直せたら、私自身ももち直しますが、でなければ、私は破滅です。」(同上、p.200、1868年7月19日)
調子が悪い大きな原因は長女ソフィヤの死であろう。この年1868年2月に長女ソフィヤが誕生した。ドストエフスキーが46歳になって初めて授かった子供である。それが3か月後の5月に肺炎で急死する。ドストエフスキーの絶望はマイコフ宛て5月18日、6月22日の手紙、アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』「外国放浪」の章、第5節などにある。この生涯最大級の不幸の中で『白痴』の執筆は続いた。
『白痴』の評判のよさは初めの方だけだったらしい。
先に挙げた姪ソーニャ・イワーノワ宛て1869年1月25日の手紙には続けて、
「・・・ここに引きこもっていては、長編についてのロシアの一般読者の意見はまったくわかりません。最初のうちは二度ほど、長編に対する感激の賞賛にみちた、いくつかの新聞の切り抜きを送ってもらいました。でも今や、いっさいの意見がとうに鳴りをひそめてしまったのです。しかし何よりまずいのは、《ロシア報知》の出版社たち自身の意見をぼくがまったく知らぬという点です。」(新潮社版全集第21巻、p.163、原卓也訳、1869年1月25日)
ドストエフスキーはロシヤに帰りたくてしょうがなかった。外国と外国人に対する驚くべき悪態を手紙で吐いている。また次に執筆予定だった『大いなる罪人の生涯』(『無神論』)のためにもロシヤに帰りたいと思っていた。それには6千ルーブリか少なくとも5千ルーブリが必要だと書いている。
後日のソーニャ宛の手紙では、
「しかし、ペテルブルグから率直に書いてよこしたところによると、『白痴』はたいていの人がけなしており、あの作品には欠点がたくさんあるけれど、その代りみんなが(つまり、読む人は)大きな興味をもって読んでいるとのことです。ぼくに必要なのも、ただそれだけです。また、欠点に関しては、ぼくは完全にみんなに賛成です。何よりも、欠点に対してあまりに自分に腹が立つので、みずから自分に対する批判を書きたいくらいです。」(新潮社版全集第21巻、p.167~168、原卓也訳、1869年3月8日)
『白痴』関連で、ストラーホフに宛てた手紙はドストエフスキーの創作観があって有名である。
「・・・私は現実というものについて(芸術における)独特の見方をしていて、多くの人がほとんどファンタスチックで、例外的と呼んでいるものが、私にとってはどうかすると現実的なもののいちばんの本質をなすことになるのです。その現象がありふれたものであることや、それに対する公式的な見方は、私に言わせれば、まだリアリズムではなく、むしろその反対です。――新聞のどの号を見ても、きわめて現実的な事実、きわめて異様な事実の報道に接することができます。(中略)それらは現実なのです。(中略)
はたしてファンタスチックな私の『白痴』こそが現実ではないでしょうか、しかももっともありふれた現実では! そう、いまこそ、大地から切りはなされたわが国の社会層にはあのような人物像があるはずなのです。(後略)」
(新潮社版全集第22巻、p.75~76、江川卓訳、1869年2月26日)
公表当時はドストエフスキーが希望していたほど高く評価されなかったが、後年になってドストエフスキーが『白痴』の評判を書いた、次の書簡も有名である。
「・・・貴方が、どれよりも優れた作品として『白痴』をあげておられるのが気に入りました。実を言うと、私はそういう意見を、少なくとももう五十回も耳にしているのです。この本は毎年売れていますし、年々売れ行きが増しているほどです。いま『白痴』のことを申しましたのは、あれを私の最良の作品だと言ってくださるすべての人が、何か特殊な頭脳構造をもっておられて、それがいつも私をたいそう驚かせ、また好ましく思われるからです。(後略)」(同上、コヴネル宛、p.492、1877年2月14日)
この書簡を書いた時点で、カラマーゾフを除く創作は完成している。生前、カラマーゾフを除けば公表時に評判になり代表作とみられていたのは『死の家の記録』と『罪と罰』である。本書簡によれば『白痴』も一定の一般の評価を得ていたらしい。
小説の特徴について
ドストエフスキーに対しては小説愛好家の好き嫌いが激しい。ドストエフスキー好きの中でも『白痴』の評価は分かれるだろう。それは読者各自の問題であろうが、本作の特徴は何か。
ドストエフスキーの他の作品と比べて静謐、と言ったら言い過ぎだろうが、他の作品のように犯罪を巡る激しさが基調をなしている小説ではない。それでいてドストエフスキー的なのである。色に例えるとドストエフスキーの多くの小説は暗い色彩だが、『白痴』は日本語から自体そうであるように白であろう。
カラマーゾフのところで述べた、ワーグナーの『ニーベルングの指環』の中で対応を捜すと「ジークフリート」に違いない。
気になるところを挙げれば、あまりうまく組み立てられた小説に見えない。第1篇はまさに怒涛のドストエフスキー的展開である。列車内、エパンチン将軍家、イヴォルギン将軍家、ナスターシャ宅での出来事が一日のうちに起こり、読者をひきつける。公表当時、最初の方の評判が良かったとは納得できる。
それが第2篇に入ると伝聞体で始まり、調子が低くなる。アグラーヤとの恋や遺産請求、イッポリートなど話題は多いが、ナスターシャはどこかに行ってしまう。
モームはその著『世界の十大小説』(1954)の中でドストエフスキーを論じている。ドストエフスキーの創作態度は霊感に絶対の信頼を置いているとある。
「一篇の小説を構成するには、首尾一貫した精神を必要とする。各部分がそれぞれなるほどと思わせるように前の部分につづき、最後に全体が完全なものになって、未解決の部分が一つも残っていないという風に、題材を秩序正しく並べ得る論理的な精神を必要とする。ところが、ドストエフスキーにはそういった才能が大してなかった。」
(岩波文庫、(下)、西川正身訳、1997年、p.224~225)
この指摘は『白痴』にはもっともらしく聞こえる。『悪霊』も同様である。代表作である罪と罰やカラマーゾフはうまく出来ている。代表作とされてきた所以のひとつであろう。
黒澤明の映画『白痴』について
本小説を原作として、昭和26年に黒澤は日本に舞台を移し映画化している。一般に文学(小説)とその映画化については次の様に言えないか。
まず小説と映画は別物である。映画化される場合はあくまで原作は基に過ぎなく、短縮や脚色されるのが普通である。出来は映画としての出来で判断すべきであって、原作と異なるから良くないなどとの批判は妥当と思えない。
もう一つは映画化に向いている作家とそうでない作家がいる。トルストイは映画向きで、ドストエフスキーはあまりそうでないように思える。
黒澤の映画は当初、4時間を超える長尺として制作されたが、会社から長すぎると指摘され、現在は3時間弱の版しか残っていない。今回『白痴』を読み返したので、久しぶりにこの映画『白痴』を観て、感心した。正直この映画は原作を読んだ者が分かる映画ではないかと思った。映画会社の幹部は原作を読んでいないので面白くないと評価したのではないか。映画を観て、原作を知ろうとする者はいるだろう。黒澤の映画はむしろ原作の既読者向けと思ったという意味で、上に述べた自分の一般的理解と異なっていた。
[翻訳について]
木村浩訳
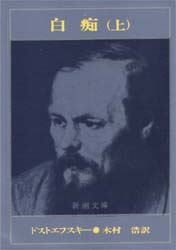
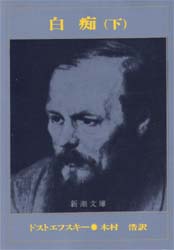
新潮文庫、上巻、昭和45年、600頁、560円(昭和63年31刷)
下巻、昭和45年、あとがき、560頁、560円(昭和63年19刷)
望月哲男訳

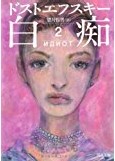
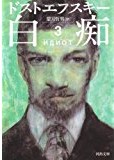
河出文庫
1、2010年、『白痴1』解説、395頁、750円
2、2010年、522頁、950円
3、2010年、ムイシキンの時間、435頁、940円
米川正夫訳


岩波文庫
上、1994年、627頁、748円
下、1994年、555頁、748円
河出書房グリーン版世界文学全集III-11巻、12巻
11巻、昭和39年、解説(荒正人)、491頁、390円(昭和42年3版)
月報:米川正夫「「白痴」初訳の頃」、近田友一「『白痴』の賭け」、「読者サロン」
12巻、昭和40年、年譜、解説(荒正人)、519頁、390円(昭和42年3版)、『初恋』『貧しき人々』併収
月報:磯田光一「昭和史におけるドストーエフスキイ」、近田友一訳注「ドストーエフスキイの言葉」、「読者サロン」
河出書房カラー版世界文学全集45巻
昭和44年、年表、解説(山崎正和)、514頁、750円、挿絵:アンドレ・マッソン
しおり:大原富枝「レニングラードの霧雨」
小沼文彦訳
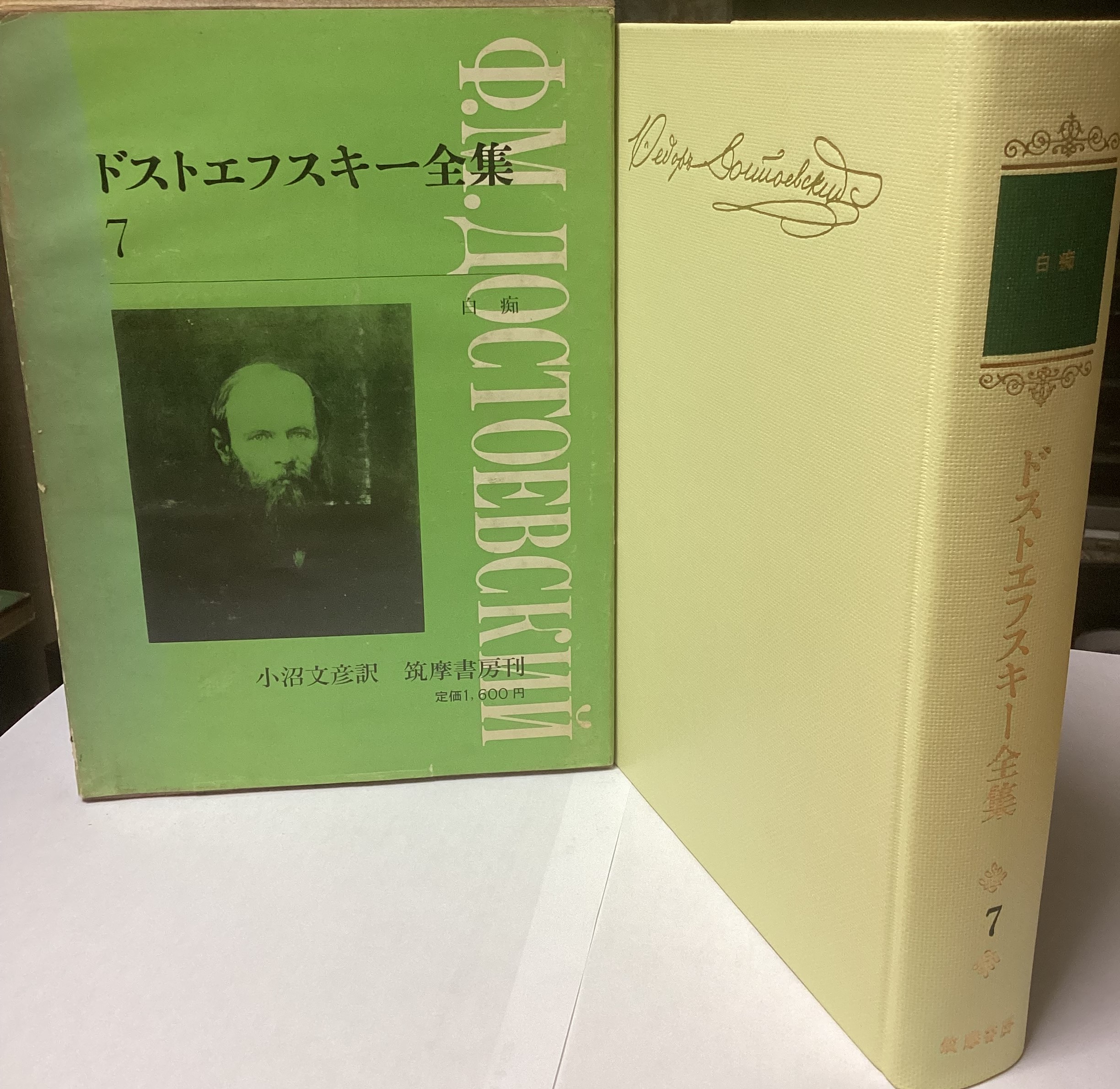
筑摩版小沼訳全集第7巻
昭和38年、訳注、あとがき、623頁、1,600円(昭和40年5刷)
月報:唐木順三「ドストエフスキーと私 1」、大江健三郎「ボールドウィンとドストエフスキー」、岩間徹「ドストエフスキーの時代 4」
北垣信行訳
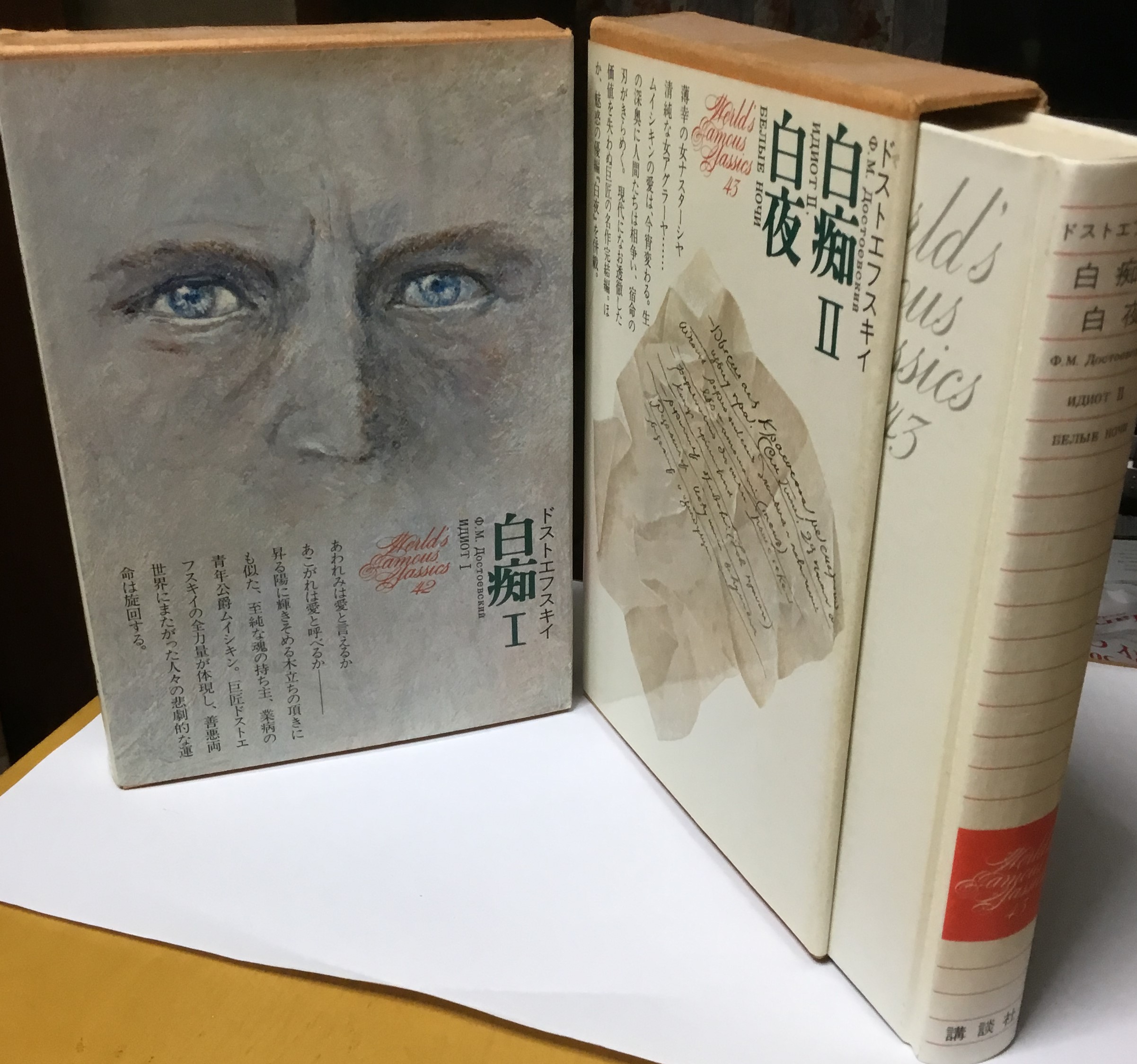
講談社版世界文学全集第42巻、43巻
I、1974年、解説、解題、年譜、437頁、720円
II、1975年、解説、436頁、720円、『白夜』併収
亀山郁夫訳
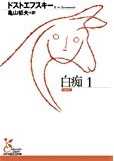
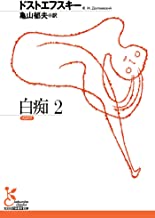

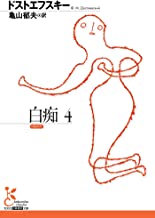
光文社古典新訳文庫
白痴1 本文、読書ガイド、466頁、2015年、860円
白痴2 本文、読書ガイド、403頁、2017年、860円
白痴3 本文、読書ガイド、389頁、2018年、880円
白痴4 本文、読書ガイド、年譜、訳者あとがき、475頁、2018年、1,040円
中山省三郎訳
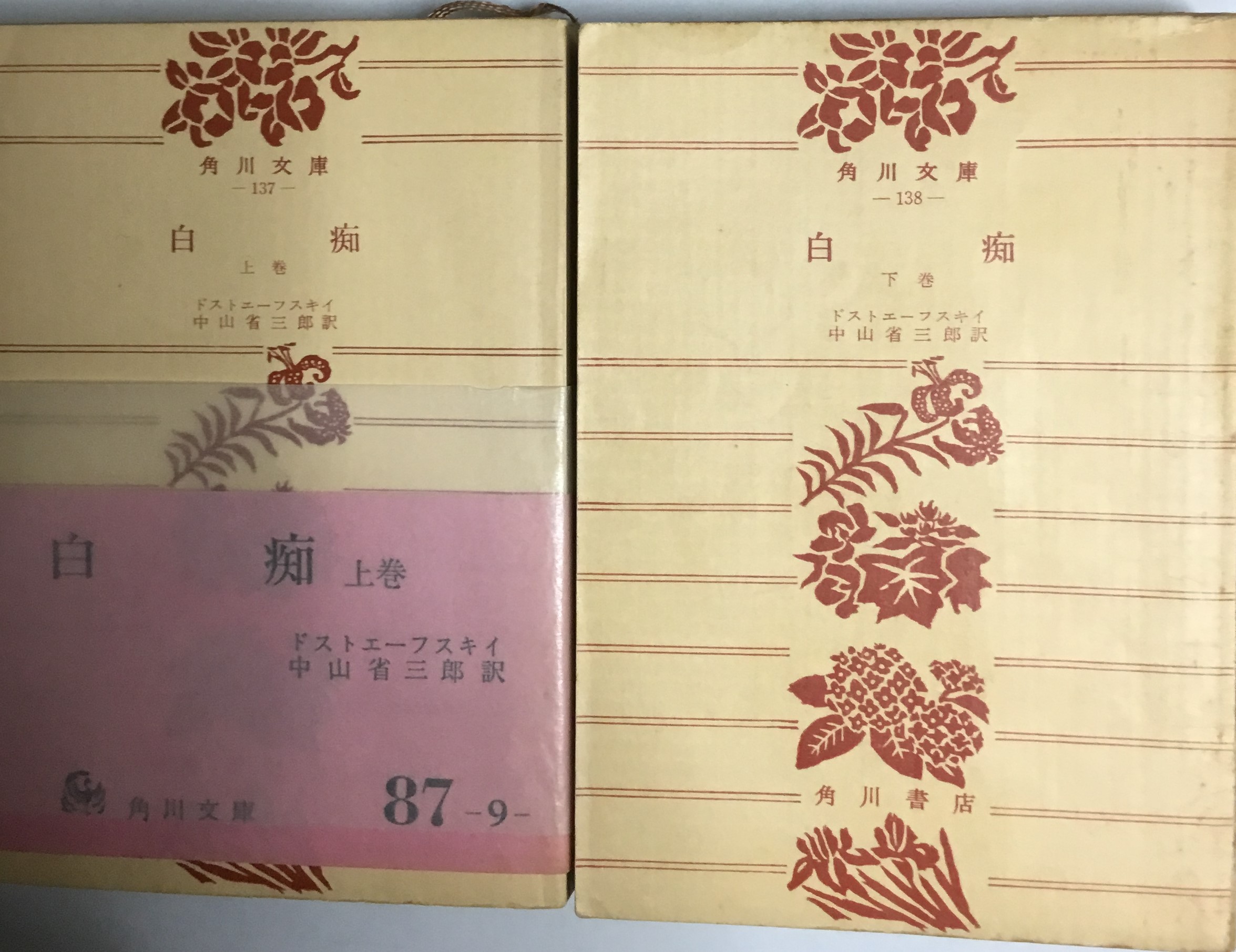
著者名はドストーエフスキイ、角川文庫、これは改版合本版
上、本文、訳注、582頁、昭和43年、240円(昭和46年6版)
下、本文、訳注、解説(横田瑞穂)、年譜、552頁、昭和43年、値段不明、古本で帯がないから。角川文庫は昭和43年当時既に定価を奥付でなく帯・カバー表記にしていた。
なお現在、中山訳『白痴』はKindleで極めて安価で読める。
他に
河出版米川訳全集第7~8巻(昭和44年)
木村浩訳新潮社版全集第9~10巻(1978)
『永遠の夫』
1870年、「ザリャー(黎明、暁)」誌に発表。[梗概]
(ネタバレが書いてある)ヴェリチャーニノフは気になる男を見かける。それがかつて知っていたトルソーツキイとわかる。実はかなり前、ヴェリチャーニノフはトルソーツキイの妻と関係があった。ヴェリチャーニノフは、その妻は亡くなったと聞かされる。トルソーツキイは娘がいる。それを聞くとヴェリチャーニノフは自分の娘ではないかと思う。娘を自分の知り合いの家に連れていき世話をしようとする。しかし病弱な娘は亡くなる。
トルソーツキイはその後、少女と言ってもいいくらいの娘と結婚しようとし、ヴェリチャーニノフをその家族に引き合わせる。ヴェリチャーニノフはその家で人気者になるが、トルソーツキイは嫌われている。少女は結婚する気はないとヴェリチャーニノフに言う。
二人が家に帰ってから青年がやって来る。彼は少女と結婚の約束をしていると、トルソーツキイに言う。その夜、ヴェリチャーニノフは病気がひどくなりトルソーツキイは助ける。しかし明け方にトルソーツキイは恐ろしい行為に出る。
後日談があって、ヴェリチャーニノフは再婚したトルソーツキイに出会う。妻は若い将校を連れていた。
[感想のようなもの]
トルソーツキイはドストエフスキーの小説に出てくる一つの典型的人物。卑屈でマゾ的、いきなり高圧的態度に出る、などドストエフスキー好きにはおなじみの人間である。我々も日常は普通にふるまっているが、時には激情的になって内心をぶちまけたいと思う。多くは我慢している。ドストエフスキーの登場人物はそれをそのまま言動に出す。
主人公は二人いてトルソーツキイとヴェリチャーニノフである。トルソーツキイは変な人とすぐわかるが、ヴェリチャーニノフもあまりまともに見えない。浮気して子供をつくってもあまり気にかけない。ヴェリチャーニノフはドストエフスキー自身をモデルにしているらしい。正直ドストエフスキーは付き合う相手としては楽しい人ではなかったのだろう。
題名について
『永遠の夫』という題を亭主になるしか能のない者、と説明している場合もあるが、江川卓の説明が分かりやすい。(集英社世界文学全集第43巻、1979年、p.450)要約すれば次のようになる。
これは「永遠の情人」ドン・ファンに対応する。永遠に(いつも)寝取られている亭主、という意味である。意訳すれば「万年寝取られ亭主」となる。(ここまでが江川の要約)小説を最後まで読めば分かる。
最近流行りの片仮名を多用した、今風の訳名を考えると『オールウェイズ コキュされ男』となろうか。
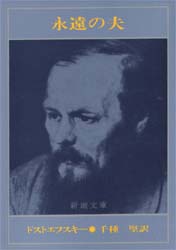
千種堅訳、新潮文庫、258頁、昭和54年、320円(平成元年14刷)
米川正夫訳、河出グリーン版世界文学全集第2期第10巻、昭和38年
筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和43年)
河出版米川訳全集第10巻(昭和52年)
千種堅訳新潮社版全集第8巻(1978)
水野忠夫訳集英社ベラージュ版世界文学全集第43巻(1979)
『貧しき人々』から『鰐』までは
こちらへ
『罪と罰』等は
こちらへ
『悪霊』は
こちらへ
『未成年』は
こちらへ
『カラマーゾフの兄弟』は
こちらへ